出版社内容情報
入浴する、トイレで用を足す、蛇口から清潔な水を汲んで飲む──水で清潔を保つ現在の日本の日常は世界の諸相、日本の歴史の上で普遍的なものなのか。温暖化で水資源への注目が高まる今、日本の歴史、世界の文化から、水と人との関係を照らしだす。
内容説明
インド・ヒンドゥー教徒たちは汚穢あふれる聖なるガンジス川で沐浴し、イスラム教徒たちは水で浄めた身でなければモスクへ入ることを許されない。十字軍時代のキリスト教聖職者たちは、ローマ風呂での乱れた風俗を嫌い、イスラム教への対抗のため、身体を洗わず、糞尿の上に平然と座すことで聖者とあがめられた者もいた。江戸っ子の風呂好きは有名だが、最初に風呂の入浴を始めたのは京の公家たちだった。幕末明治の江戸東京では公衆浴場が大流行したが、陸軍医として清潔を旨としていた〓外は、自宅に風呂があるものの、金盥にためた湯を使い手拭で身体を拭うのみだった。日本の歴史、世界の文化から、水と人、清潔の概念の諸相を照らし、その関係の変遷をたどる。
目次
序章 豊富な水と不足する水―すべての根源、インドの場合
第1章 水事情のいま
第2章 水と「清潔」という概念
第3章 水と衛生行政―英国の場合
第4章 江戸の水、明治の水
第5章 水の効能―水治療・温泉・海水浴
第6章 〓外の手拭、北里の大風呂―清潔と近代
終章 変化とは―水の不足と世界の国々
著者等紹介
福田眞人[フクダマヒト]
京都市出身、名古屋大学名誉教授。学術博士。京都大学工学部卒、東京大学大学院(比較文学比較文化)修了。オックスフォード大学医学史研究所、ハーヴァード大学科学史学科客員研究員、デリー大学客員教授、日本学術振興会システム研究センター主任研究員、名古屋外国語大学教授などを経て東華大学(上海)客員教授。専門は比較文化、医学史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
やいっち
ゲオルギオ・ハーン
紙狸
ひなぎく ゆうこ
-
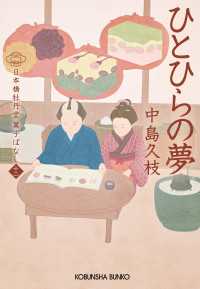
- 電子書籍
- ひとひらの夢~日本橋牡丹堂 菓子ばなし…
-
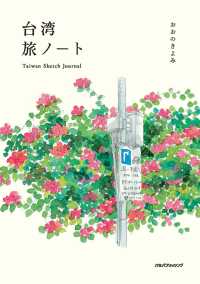
- 電子書籍
- 台湾旅ノート







