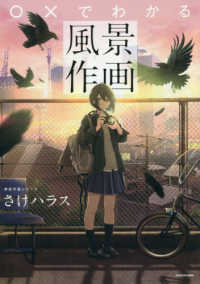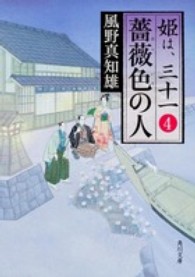出版社内容情報
「慰安婦問題」をめぐる朝日新聞の報道と、朝日新聞社を相手に起こした集団訴訟の 末の詳細を記録した書。2014年8月の検証記事の執筆に参加し、その後も取材を続けてきた記者が、置き去りにされ続ける問題の本質を徹底追求する。
内容説明
朝日新聞を相手に起きた「三つの訴訟」や、「慰安婦像撤去訴訟」「植村隆氏の訴訟」「第三者委員会報告書」…。2014年8月の朝日新聞・慰安婦問題検証記事の執筆に参加し、一連の訴訟や保守・右派の動きも徹底取材してきた記者による克明な記録。慰安婦問題の本質とは何か―。
目次
慰安婦問題とは
問題のこれまで
保守・右派の台頭
二〇一四年検証記事
「慰安婦問題を考える」
保守・右派の提訴
「朝日新聞を糺す国民会議」の訴訟
「朝日新聞を正す会」の訴訟
「朝日・グレンデール訴訟」
米国での慰安婦像撤去訴訟
植村隆・元朝日新聞記者の訴訟
訴訟後も続く運動
著者等紹介
北野隆一[キタノリュウイチ]
1967年岐阜県高山市生まれ。90年東京大学法学部卒業、朝日新聞社入社。新潟、延岡、北九州、熊本をへて東京社会部次長を務め、2014年から編集委員。皇室、北朝鮮拉致問題、部落問題、ハンセン病、水俣病などを取材(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
小鈴
19
(1)慰安施設は満州事変の翌年の1932年から1945年まで。きっかけは第一次上海事変の日本兵による中国人女性強姦事件で日本から軍専用に慰安婦団を招いたこと、軍全体に広がったのは1937年7月の盧溝橋事件以降、慰安所が一気に増加、戦局の拡大で広がる。1937年9月「野戦酒保規定」で慰安施設が明記、制度化された。慰安婦には日本人/植民地の朝鮮人・台湾人/占領地の女性、左から右の順で「強制」が増す。当時の日本では売春婦は21才以上(注記)しかつけなかったが、植民地はそれが適応されず未成年女性も対象に。2020/10/10
小鈴
18
なんだか込み入ってよく分からない慰安婦問題の全体像を見通すことができて分かりやすい。読書中だが大切な点をメモ。◆軍や警察の公文書から見る実態(永井和教授へのインタビュー)。「慰安所は民間業者が不特定多数の客のため営業する通常の公娼施設とは違います。軍が軍事上の必要から設置・管理した将兵専用の施設であり、軍の編成の一部」。「陸軍大臣が日中戦争開始後の1937年9月に『野戦酒保規定』という規則を改定(略)。軍隊内の物品販売所「酒保」に『慰安施設を作ることができる』との項目を付け加える内容」→2020/10/06
小鈴
15
(2)朝日新聞VS右派保守の対立。詳細は余力があればあとでまとめるが、右派保守は朝日新聞の慰安婦報道が①「世界に影響を与えた」せいで少女像が各地に設置されたと捉えたこと、韓国の慰安婦は軍が②「人狩り」のような物理的強制力をもって集めたものではない、虚偽だというところで戦っている。個人的には、保守も慰安所や慰安婦の存在を認めていることを知ったのが成果かな。朝日新聞が吉田清治の証言を検証して謝罪したのは第二次安倍政権の成立を予見して国会で尋問される可能性を見越していたのは初めて知った。緊張感があったんですね。2020/10/10
小鈴
13
慰安婦問題の複雑さは、(1)慰安施設が満州事変の翌年の1932年から敗戦まで続いたこと、13年間の戦争と戦争の進行によって慰安婦とされた状況が変化していること、(2)国内の慰安婦問題の言説が朝日新聞対保守、右派の対立で更に複雑化したこと、だと理解した。特に(2)は基本的に保守雑誌やネットではよく見かけてもテレビなどではたいして取り上げられず、知る者はこの問題に詳しいが知らぬ者はまったく知らず、ネットへアクセスすると右派、保守言説の真偽不明な言説があふれてうんざりする状況だ。問題を二つに分けてまとめる。2020/10/10
tellme0112
8
ようやく読み終わった。長かった。最初読むのが辛かったが、裁判始まってからは淡々と、進む。「勝訴ではなく原告敗訴」に、誠実さが現れているように思った。のりこえねっとTV100回記念の日に。2020/12/09
-

- 電子書籍
- 冥途大学幻象ゼミナール(40) com…