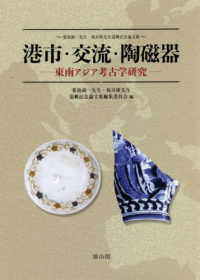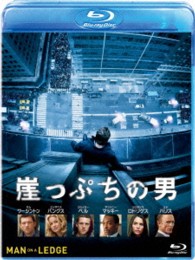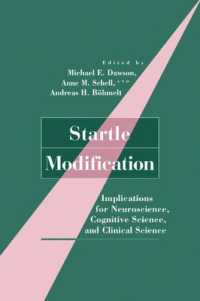出版社内容情報
『朝鮮民謡選』を読み耽った少女時代。30歳を過ぎた頃、心に残った仏像がすべて朝鮮系であることに気づく。50代で学び始めたハングルははたして魅力あふれる言葉だった。隣国語のおもしろさを詩人の繊細さで紹介する。
内容説明
ハングルを学ぶようになった動機、ともに学ぶ人びとのこと、日本のいち方言との類似点、ユーモラスな諺や表現の数々―。隣国語のおもしろさを、韓国への旅の思い出を交えて、繊細に綴った珠玉のエッセイ。日韓の習慣や意識の違いをみつめて紡いだ言葉がいまなお胸を打つ。
目次
扶余の雀
1 はじまりが半分だ
2 日本語とハングルの間
3 台所で匙を受けとった
4 旅の記憶
5 こちら側とむこう側
著者等紹介
茨木のり子[イバラギノリコ]
1926年生まれ。詩人。2006年逝去(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kuukazoo
21
韓国語学習者としてはいつかは読んでおかねばと思ってずいぶん積読になっていた。1986年発行。NHKラジオの語学講座にハングルができたのが1984年。当時は韓国語を学んでいると言うと判を押したように動機や理由を尋ねられ困惑したというが今では推し活で十把一絡にされてしまう(^_^;)そうした学びの思い出に始まり、韓国語そのものへの興味、旅先で会った人との交わり、食や器や骨董、そして詩人たちのことなど素直で軽やかな語り。知らないことも多かったのでいつかまたこの本に戻ってくるかも。2024/08/12
るむ
10
韓国語を勉強している&行きたいと思っているので、読んでみました。1986年に書かれた本ですが、古い感じがせず、楽しい!料理や文化も興味深いです。しかしそれだけでなく、日韓関係にも触れています。日本の終戦記念日が、韓国の解放記念日。なんとも言えない気持ちです。浅川巧さんと東柱さんについても知りませんでした。韓国についての知識が浅すぎでした!2023/11/13
よんよんおばさん
9
図書館本。著者が学び始めたのは70年代。そこで出会った教師や友人の話や、日本語の方言との類似点や、文化の違いなどが、温かい目線で語られていました。 韓国語というと北がクレーム、朝鮮語というと南がクレーム。そこでハングル講座というらしい。なるほどNHKでもハングル講座だなと納得しました。 同志社大学に留学した尹東柱の獄中死は知らなかったし、親御さんはどんなに辛かったかと悲しくなりました。2024/02/05
kokekko
9
「ハングルを勉強していると言うと、『ほう、してまたどうして?』と尋ねられる」という言葉から始まる本書だが、隔世の感がある2023年である。iTunesには韓国アイドルの曲があふれメイクと言えば韓国流だ。しかしここに描かれている「モッ」に相当する精神性などは現在のブームでも知る由がなかった。詩人である作者の紹介してくれる、単語の響きやメンタリティ、オノマトペなどの面白さ。とても惹かれる。韓国語の勉強がなかなか進まないのが悩みだったのだが、もう少し頑張れるような気がしてきた。2023/12/03
Shun'ichiro AKIKUSA
9
最高の語学エッセイのひとつだと思う。ハングルや韓国の文化について、著者の率直な目線が光っている。 著者がハングルを学びはじめた当時の状況などわかっておもしろい。いまよりずっとマイナーな語学だった。2023/04/30