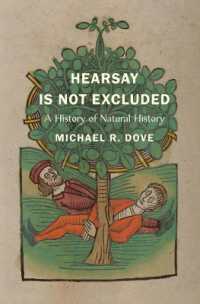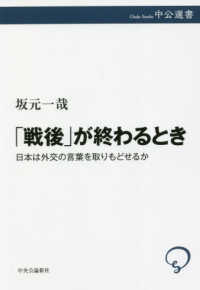出版社内容情報
たいしてできもしないのに自信満々な人や、人よりできると思っている上司をよく見かける。実は、脳はうぬぼれやすいのだという。毎朝100~200本の学術論文に目を通す人気脳研究者が脳と科学の最新知見をつづる。占い師しいたけ.さんとの対談も収録。
内容説明
記憶力を高める方法とは?結婚後に絶望するカップルって?iPS細胞に心は宿るの?人気脳研究者が日々の研究や科学の最新知見を通し、「脳という装置をどんな風に考えたらいいか」に思いを巡らせて綴った一冊。知れば知るほど面白い脳のクセ。
目次
1 脳のクセを知る
2 記憶とは何か
3 ヒトをヒトたらしめるもの
4 「気持ちいい」を科学する
5 見えない世界
6 未来を考える
著者等紹介
池谷裕二[イケガヤユウジ]
1970年静岡県生まれ。薬学博士、東京大学薬学部教授。2013年、日本学士院学術奨励賞を受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。