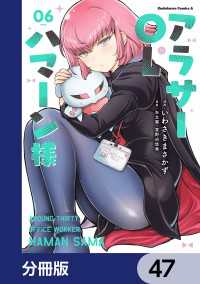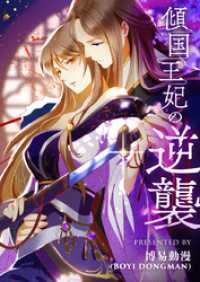出版社内容情報
信長は朝廷との共存を望んでいた! 「楽市楽座」は信長のオリジナルではなかった! 世間では相変わらず「超人的な信長像」が人気だが、本当の信長はどんな人物だったのか? 最新研究で明かされた、新たな人物像をめぐる14本の画期的歴史評論集。
内容説明
日本人は信長が大好きだ。その破天荒な性格、革新的な政策や合戦方法が私たちを魅了する。だが、近年の研究でそれらが真実ではないことがわかってきた。本当の信長はどんな人物だったのか?第一線の研究者たちが一次史料を駆使し、新たな人物像に迫る!
目次
第1部 政治権力者としての実像とは(信長は、将軍足利義昭を操っていたのか;信長は、天皇や朝廷をないがしろにしていたのか;信長は、官位を必要としたのか;織田・徳川同盟は強固だったのか;信長は、秀吉をどのように重用したのか)
第2部 信長は軍事的カリスマか(桶狭間と長篠の戦いの勝因は;信長は、なぜ武田氏と戦ったのか;信長を見限った者たちは、なにを考えていたのか;明智光秀は、なぜ本能寺の変を起こしたのか;信長は、なぜ四国政策を変更したのか;信長家臣団における「勝ち組」「負け組」とは)
第3部 信長の経済・文化政策は特筆されるか(信長の流通・都市政策は独自のものか;信長は、宗教をどう捉えていたのか;信長は、文化的貢献をしたのか)
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
倍の倍のファイト倍倍ファイトそっくりおじさん・寺
68
新型コロナに翻弄された今年の大河『麒麟がくる』。ドラマ自体への不評好評はそれぞれあろうが、登場する武将達のキャラクターが新しい。明智光秀は主人公だからアレにせよ、あの信長や秀吉、松永久秀や足利義昭の描かれ方は画期であると思う。それもこれも、きっとこういった学者や研究者が、古いテキストとガップリ組み付いて出した論考の力は少なく無かろう。本書を読めば、信長が傑出したリーダーではないのがわかる(これはどんな武将でも史料に当たればそうだろう)。古いものをきちんと読めば、新しいものが生まれる。読むという行為は素敵。2020/11/03
ホークス
46
元本は2014年刊。型破りで革新的とされる信長についての研究14編。本書を読むと、信長を革命家とは言えないようだ。前例や礼儀も重んじるし、セコい事もする。信長の称した上総介(かずさのすけ)は、実は今川家が代々使ってきた官途。要するに嫌がらせで名乗っていたのだ。楽市楽座は信長の独創ではないし、桶狭間や長篠の戦いも天才的とは言えない。有能で果断で冷酷、かつ幸運だった事は確かなようだ。本書で面白いのは、信長を通して知る戦国時代の色んな実態。京都の仏教界がどんな勢力図で何を争っていたかなど中々興味深い。2021/11/30
金吾
27
そうだろうなあと感じる説もあれば、そうだったのかと感じる説もありました。研究者は新たな史料が出てくる喜びを感じながら研究をしていくことが伝わりました。第2部が面白かったです。2024/03/02
さきん
27
最近の知見も合わさってきて、何でも前例を壊す信長という従来のイメージは軟化し、先人の画期的な取り組みをうまく取り入れてPRする信長像というのができつつあるを感じる。力が正義をいいつつもそれを後追いでも権威付けする朝廷のあるなしが、敵対者を従わせるためにもとても重要。本能寺の変に四国外交が大きく影響しているという指摘は、土佐っ子としてわくわくする。家康は何回も天下を諦める経験をしているのに、最後に天下を勝ち取るのはすごい。2022/02/05
サケ太
22
やはり、信長。あらゆる創作の中で、多くのレッテルを貼られ続けた信長の最新研究をまとめた一冊の復刊。その為、現在まで多くの一般書で触れられていた内容もある。が、それらの研究がまとめて読める。更には、家康との同盟関係、信長の「能力主義」の実態、配下の謀反の理由や宗教に対する接し方についてなど、興味深く読める。『同時代史料に基づきつつも、史料の解釈をめぐって意見の相違が見られる。研究とはそのようなものである。より合理的に解釈することによって、その正確性を増していく。そうした作業が続けられているのが現状である。』2020/10/13