内容説明
出会ってすぐに家へ招かれ、外食すれば知らぬ間に誰かが代わりにお勘定、町を案内してくれたちょいワル青年はお年寄りに親切。「怖い」「危険」とイメージされがちな国の人たちは世界一旅人にあったかい。沢山の出会いから日本が知らなかったイスラムの意外な姿が見えてくる。
目次
第1章 チュニジア
第2章 ヨルダン
第3章 パキスタン
第4章 モロッコ
第5章 オマーン
第6章 エジプト
第7章 シリア
著者等紹介
常見藤代[ツネミフジヨ]
1967年群馬県生まれ。ノンフィクション写真作家。上智大学卒業。保険会社に3年間勤務した後、フォトジャーナリストを目指しアジア・アフリカを放浪。その後1年間エジプトにてアラビア語を学び、以後エジプトなど中東・イスラム圏を取材。2003年からエジプトの砂漠で遊牧民の女性サイーダと暮らしながら撮影。彼女をテーマとした写真展を行い、その後も各地で写真展、講演会を開催。2012年、第19回旅の文化研究奨励賞受賞(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
335
これを読むと、イスラム諸国については何も知らないのに誤解していたのだと思う。我々の該博な認識ではイスラムといえば、さぞかし女性をないがしろにしているのではないかと思いがちなのだが、彼女によれば全くそうではないのだ。チュニジア(ここはまだしも)、ヨルダン(手ごわそうだが、本書を読めばそうでもなさそうな)、パキスタン、モロッコ、オマーン(生涯に行くことがあるのだろうか)、エジプト、シリア。ほんとうに貴重な旅の記録。先入観を捨てれば、世界はまったく別の様相を見せてくれるのだろうか。こんな旅をしてみたいものだ。2016/01/26
どんぐり
61
1週間前に写真家・作家の常見藤代さんの写真展「イスラーム ヴェールの向こう」を見て、早速この本を読んだ。イスラーム圏のチュニジア、ヨルダン、パキスタン、モロッコ、オマーン、エジブト、シリアを女ひとりで訪れ、行く先々で知り合った人の家々に泊まり、そこで出合う異文化への関心と旅の記録。イスラームの人は、女性にやさしいね。2018/05/06
morinokazedayori
46
★★★★チュニジア・モロッコ・エジプトなどイスラム諸国の滞在記。著者はノンフィクション写真作家。一般の信者たちはとても善良で、女性の旅人に優しく、食事や宿を提供し、温かく迎え入れる。結婚観は日本と大きく異なる。親族一同で納得できる相手を選び、本人同士は結婚式まで会わないことも。女性が夫以外の男性の前で顔以外の肌を露出しないことで、夫にとって妻だけが魅力的な女性に見える。そのことで、新鮮で幸せな結婚生活が長く続くという。異文化に触れると新しい視点を得て、今の生活の何がよくて何が悪いのか、考えさせられる。2016/06/16
こばまり
41
2012年の『女ノマド、一人砂漠に生きる』以来注目していた筆者の文庫新刊。イスラム教徒が旅行者に優しいのはかつて私も体験したので分かりますが、常見さんのお人柄に負うところも多いのでは。いみじくも発行が今般の人質事件と時期を同じくしてしまい、この本が日本国内でどのように受け止められるか気になります。2015/01/29
これでいいのだ@ヘタレ女王
32
イスラム圏の様々な国を一人旅をした女性の手記。少しずつ地域差はあるが、どこの地域の人々も人懐こく、優しく、家に招き泊めてくれる寛容さがある。真のイスラムの教えは徳を積むと来世はよくなる。と信じられ、弱い立場の女性は労らなければならないという教えのもとに大切に扱われている。原理主義やら 物騒な渦中に優しく穏やかな彼らがいるのが悲しい。娘の友人も近年までイスラム圏をたびしていたが、手料理でもてなされ、宿泊しているから本著に書かれていることは事実でろう2015/03/12
-
![そのメイド、危険につき[1話売り] story9 花とゆめコミックス](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-2162614.jpg)
- 電子書籍
- そのメイド、危険につき[1話売り] s…
-

- 電子書籍
- 彼女、秘密の君主【タテヨミ】第67話 …
-
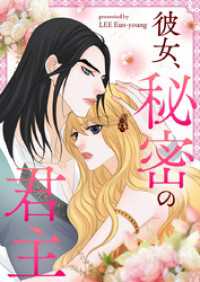
- 電子書籍
- 彼女、秘密の君主【タテヨミ】第68話 …
-
![秘蜜の森[ばら売り]第5話[黒蜜] 黒蜜](../images/goods/ar2/web/eimgdata/EK-1205632.jpg)
- 電子書籍
- 秘蜜の森[ばら売り]第5話[黒蜜] 黒蜜





