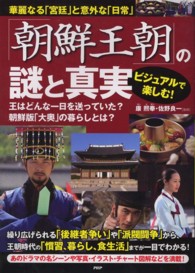内容説明
1869年の開通いらい、世界情勢の鍵を握る要所として注目を浴びているスエズ運河―。その起源ははるか古代エジプトにまでさかのぼる。ファラオの時代から現代まで、地中海と紅海を結ぶ運河を巡って繰り広げられた4000年の興亡を軸に、ジャーナリストの目で壮大な歴史の流れを描く。
目次
第1章 ファラオの運河
第2章 モーセの道
第3章 クレオパトラとトラヤヌスの時代
第4章 メッカに向かって
第5章 移ろいゆくカリフの興味
第6章 十字軍のなかで
第7章 ナポレオン・ボナパルトの登場
第8章 レセップスの構想力と行動
第9章 1869年11月17日の輝き
第10章 戦争と自由通航の試練
第11章 ついに来た国有化の日
第12章 国有化後の展開
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
coolflat
17
スエズ運河を軸としたエジプト四千年史。ただ紀元前二千年から17世紀までは単なるスエズ運河周辺史となっており、肝心なスエズ運河自体が本格的に出てくるのは、1671年にライプニッツがルイ14世にスエズ運河の開掘を進言したのが始まり。以下の流れとしては、17世紀のライプニッツの進言→18世紀後半のナポレオンのエジプト遠征(目的の一つにスエズ地峡の開掘があった)→1869年のレセップスによるスエズ運河建設(レセップスの父親がナポレオンの外交官であり、レセップス自身はナポレオンの『エジプト誌』に強く影響を受けた)→2018/05/03
陶符
0
表題の通りスエズ運河に纏わる歴史を時系列に追っていくだけなのだが、思いの外読みやすい一冊だった。新幹線の中で一気に読んでしまった。2015/01/04
-

- 電子書籍
- ザ・平松伸二 ブラック・エンジェルズ6…
-

- 和書
- 医科生理学展望