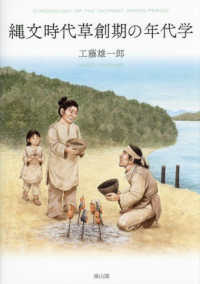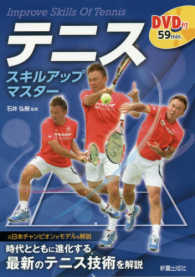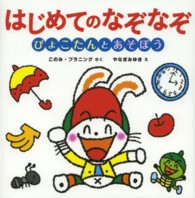内容説明
『朝鮮民謡選』をくり返し読んだ少女時代。心奪われる仏像がすべて朝鮮系であることに気づいたのは、30歳過ぎた頃。そして、あたかも、見えない糸にたぐり寄せられるかのようにして50代から著者が学び始めたハングルは、期待通りの魅力あふれる言葉だった。韓国への旅の思い出を織りまぜながら、隣国語のおもしろさを詩人の繊細さで多角的に紹介する。
目次
1 はじまりが半分だ
2 日本語とハングルの間
3 台所で匙を受けとった
4 旅の記憶
5 こちら側とむこう側
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
こばまり
56
氏が1970年代からハングルを学ばれていたとは。隣国の言葉や文化、人柄など、学習や旅、人との出会いを通して得た気付きや興味が記されているが、名著の証か、これが今読んでも一向に古びず、とても朗らかな気持ちになった。ハングルを学ぶ読者なら尚更だろう。2022/04/04
おたま
46
最近、韓国の小説を読むことが増え、また韓国の映画にも関心をもっている。ハングルという朝鮮の言葉は、まったく分からないけれど、この本はハングルという言葉を通して、韓国・朝鮮について様々なことを教えてくれる。詩人でもある著者は、やはり言葉には敏感であり、ハングルという言葉の背景に韓国・朝鮮の様々な暮らしの在り様、感性を知る。また、そこには日本の言葉との比較や、日本と韓国・朝鮮との歴史的な関係も探られていて、両国の関係やそこに絡む人々の思いも伝えてくれる。ハングルにも、韓国・朝鮮にも入門書として最適だと思う。2023/08/21
ちゅんさん
44
個人的にこれぐらいの時代を生きた人たちのエッセイを読むと背筋がシャンとして気が引き締まる。もちろん昭和という比較的近い時代が故の古さを感じるがそれが嫌な古さではないのだ。向田邦子のエッセイを読んだときもそうだった。著者が待つ繊細さや謙虚さ、感受性を感じられるこういう本をこれからも読み続けたい。2024/12/25
ケイティ
39
1970年代に50歳で韓国語を学ぼうとカルチャースクールに通学した茨木さん。講師が情熱的だったこともあり、夢中になって韓国語の魅力、面白さをぐんぐん吸収された様子が素敵。実際に茨木さんが韓国を旅した際の異文化との触れ合いが生き生きと綴られている。韓国では詩集がよく読まれることもあり、表現力も豊か。感情表現をストレートにするということは、言葉を駆使して紡ぎ、的確に伝える、響かせる創意工夫が伴う。その言葉への熱量に茨木さんは魅了されたのかもしれないと、純粋な好奇心に満ちた良書でした。2022/06/16
のせ*まり
34
韓国語を習い初めて3ヶ月。まだ簡単なハングルしか読めないけど、時々出てくる単語がわかると嬉しかった?私はミーハー心で始めたけど、茨木さんも結構ミーハー心で始めている部分もあって好感が持てる(笑)韓国語だけじゃなく、韓国と日本の歴史的背景にも触れていて辛い部分もあったけど。日本と同じく、韓国もこの30年でほんとに様変わりしたんだなぁと実感。テテがあんなに人懐っこいのは土地柄なのかと納得。韓国行きたいよー!!!! 2018/07/14