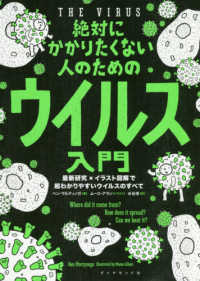感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ヴェネツィア
384
遅ればせながら、立花隆追悼の想いを込めて。本書は『日本共産党の研究』や『田中角栄研究』と並ぶ、著者の比較的初期の代表的な労作の1つ。1980年の著作なので、もう40年も前のものなのだが、農林水産省や全農中央の官僚体質は今も変わらないのではないかと思われる。もっとも、本書で紹介される「農協」は、前半の北海道の士幌や鳥取の東伯、静岡の三ケ日など先進的なものもあるが、後半では問題もまた多い。農水省についていえば、将来性を見通すことのない、相も変らぬ補助金行政であり、農協については肥大化と硬直化がそれだろう。2021/07/10
1.3manen
32
中曽根内閣の1984年頃出た本。ガットUR交渉を想起した。牛肉オレンジ輸入自由化の頃。棚田はほんとに手間がかかる。15日かかる田植え。堆肥6日。あぜつくりに10日(100頁)。今でこそ減反廃止だけど、中山間地域の宿命か? 日本農業に対する外圧はもっぱらアメリカからくる(136頁)。TPPの今日もその通り。能力がない農民に早く離農してもらわないことには、ほんとうは自立能力がある農民まで、いつまでたっても政府の保護を離れられないという状況がつづく(149頁)。2015/12/14
nobody
10
田舎では農民はふんぞり返っている。皆一様に御殿のような家に住んでいる。現代の地主は農民である。土地所有と食管という二大利権が「惰農」をのさばらせた。ブロイラーが国際価格と差がないのは、農業の中で唯一農外資本にヘゲモニーをとられ仮借なきコストダウン競争を余儀なくされ徹底的な合理化が図られたからだ。酪農が主体的に合理化・規模拡大を自然に進められるほどの実力を身につけたのは、乳価が合理化の最先端をいく酪農家の再生産を保証するラインに設定されたために、全体的に合理化を促す作用をもったからだ。このブロイラー・酪農と2025/06/27
さっと
9
およそ40年前の農業協同組合(JA)、ひいては日本の農業・農政をひとなめにした労作。ポテトチップスのふるさと士幌町農協(北海道)にはじまる個性的な単協の取り組み、米・野菜・牛肉らカテゴリーごとの動き、農産物以外のエネルギー(石油)供給元・保険会社としての顔、全国的な大票田の政治的な絡み等々、豊富なデータと綿密な取材による圧倒的な読書感。北海道米は量だけでなく質も向上、士幌は畑作に加えてブランド牛も展開、十勝の生産者発の乳業メーカー「よつ葉乳業」の成長、後日譚でもう何冊も書けそうな時の流れを感じる。2023/10/29
まさげ
4
農業について無知であったことを実感させられた。著者の緻密な取材に基づく論証は衝撃だった。2016/03/05
-
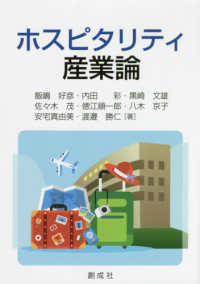
- 和書
- ホスピタリティ産業論