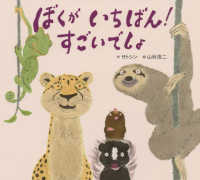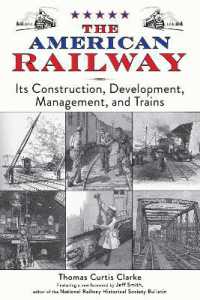出版社内容情報
総延長は、北海道をのぞいた現代の高速道路にほぼ匹敵する古代駅路。全国規模で建設されたこの直線道路網は、古代史上最大の内乱、壬申の乱を征した天武天皇が行なった政策で、律令国家のあり方を具現化したものであった。じつは直線道路のあり方は古墳時代までさかのぼる。群雄割拠から天皇中心への転換を達成した雄略天皇の時代、変革と国際化の中で律令国家の建設に突き進んだ推古天皇の時代、律令国家完成の土台を築き上げた天武天皇の時代――。時代の転換期には道路の姿も大きく変化した。やがて律令国家そのものが弱体化し、ついに消滅すると、これらの道路も変質し、消滅してしまう。古代国家の体制変化と道路のあり方を、文献資料、発掘調査の成果から読み解く。
内容説明
近年の発掘調査の増加とともに、古代の道路跡が全国各地で次々と発見されている。驚くのは、直線で舗装された道路であることだ。側溝をそなえ、広いものは幅30メートルにも及ぶ。これらは時の巨大な権力が労働力、技術力を結集し、目的を持って造ったことを物語る。道づくりの技術はどこから来たのか。なぜここに道を通す必要があったのか。道の上で何があったのか。大豪族葛城氏の繁栄を支えた道路、推古天皇・聖徳太子・蘇我馬子の経済政策と道路の関わり、壬申の乱の舞台となった要衝、全国駅制施行とともに行われた列島改造、律令制の崩壊と地方分権にともなう道路の荒廃など、古代国家の誕生から終焉までを、5~10世紀の道路の実態から読み解く。遺跡を歩く写真・地図を多数収載。
目次
第1章 葛城の道(古墳時代にも頑丈な道路を造る技術があった;造ったのは誰か;付け替えられた国道)
第2章 大和・河内の直線古道(六世紀の道路;いつ造られたのか;なぜ造られたのか;聖徳太子と蘇我馬子)
第3章 七道駅路(古代のハイウェイ;律令国家と駅路;古代国家と道路)
著者等紹介
近江俊秀[オウミトシヒデ]
1966年宮城県石巻市生まれ。文化庁文化財部記念物課文化財調査官。奈良大学卒。奈良県立橿原考古学研究所研究員を経て現職。専門は日本古代交通史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
やいっち
鯖
MASA123
京橋ハナコ
マウンテンゴリラ