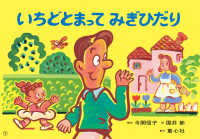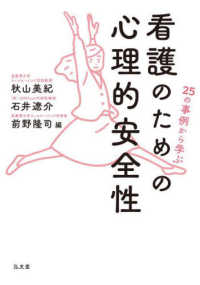出版社内容情報
★本書は『書評空間 KINOKUNIYA BOOKLOG』にエントリーされています。
内容説明
飢餓と戦争があいついだ日本の戦国時代、英雄たちの戦場は、人と物の掠奪で満ちていた。戦場に繰り広げられる、雑兵たちの奴隷狩り―。まともに耕しても食えない人々にとって、戦場は数すくない稼ぎ場だった。口減らしの戦争、掠奪に立ち向かう戦場の村の必死の営み。やがて、天下統一によって戦場が閉ざされると、人々はアジアの戦場へ、城郭都市の普請場へ、ゴールド・ラッシュの現場へ殺到した。「雑兵たちの戦場」に立つと、意外な戦国社会像が見えてくる。
目次
1 濫妨狼藉の世界(戦国の戦場;朝鮮侵略の戦場 ほか)
2 戦場の雑兵たち(口減らしの戦場;渡り歩く奉公人たち ほか)
3 戦場の村―村の城(城は民衆の避難所;安堵を買う)
4 戦場から都市へ―雑兵たちの行方(浪人停止令;「身分法」と人掃令 ほか)
エピローグ―東南アジアの戦場へ
著者等紹介
藤木久志[フジキヒサシ]
1933年、新潟県生まれ。新潟大学卒業・東北大学大学院修了。立教大学名誉教授。文学博士。日本中世史専攻
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
白隠禅師ファン
20
藤木先生の著書は実は初読了。戦国期の傭兵たちによる物や人身の掠奪、いわゆる乱取り・乱防取りやどんどん、町中に出ていく民衆etcなど自分たちが「食っていくため」の生存戦略、いわば自力救済社会ともいえる戦国期・江戸初期の様相をとらえた名著だった。2025/07/09
MUNEKAZ
19
再読。戦場での略奪や人攫い、傭兵たちの跋扈する戦国の世を百姓や雑兵たちの視点から切り取った一冊。暴力が支配する戦場を、農村が吸収しきれなかった人々の「出稼ぎの場」「公共事業」として捉えることで、のちの朝鮮出兵や天下普請にも繋がる視点を見せてくれるのがなんとも面白い。中世に満ちている暴力のベールを剥がしてみれば、今の世のと変わらない低開発に悩む地域からの出稼ぎや、雇用の調整弁としての非正規労働者の姿が浮かび上がってくる。断定的な著者の書き方が気になるが、戦国に対する見方が変わるのは確かな名著。2019/12/14
ちゃま坊
17
戦国武将ではなく雑兵の視点で戦国時代を眺めると、今までと違った世界が見えてくる。農業生産が低く百姓だけでは食えない。飢えて死ぬくらいなら戦に参加する。雑兵にとっては武士道も忠義も恩賞もない。城攻めより略奪と捕虜の人身売買に励む。兵の士気を高めるために武将は黙認する。徳川軍も武田軍も秀吉軍もみんなやってた。負ければ死ぬか奴隷になるかだ。食うための戦争なのだ。2019/08/04
futabakouji2
14
徴兵される時期に関する考察が素晴らしかった。 米を収穫する秋に農民は食べ物に困っていない。困ってないから、自分の村に入れる。大名としては農民を安く徴兵できない。しかし、飢餓に苦しみ冬、春になると食べ物に困った農民を安く徴兵する。これがひとつのパターン。んで非常事態の災害、凶作の時はもう大名、領民困った状態に陥るので他国から略奪。安定した食料を供給できる政権がないのは本当にきつい。2018/06/09
jiangkou
10
歴史好きな高校生などは是非読むべき本。欧州の傭兵文化、略奪文化はなぜ日本戦国時代なかったの?と思ってたら普通に日本の戦国時代も大部分は人狩りだったってさ。各地の狩りの事例、禁令、人質の売買も普通に行われていて中世欧州となんら変わらん状況だったらしい。農民は山城なんかにこもってそれから身を守ったらしい。2018/02/12