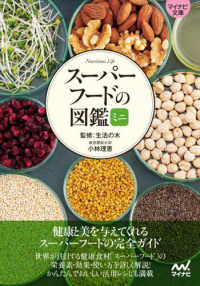内容説明
「七度の餓死にあうとも、一度の戦いにあうな」―「飢餓も恐ろしいが、戦いの方がもっと悲惨だ」。私たちの意表をつくこの格言の真実を、ことに飢餓と戦いの続いた日本の中世史のなかにさぐる。
目次
1 中世の生命維持の習俗
2 応仁の乱の底流に生きる一飢饉難民・徳政一揆・足軽たち
3 戦場の村
4 村の武力と傭兵
5 九州戦場の戦争と平和
6 中世の女性たちの戦場
著者等紹介
藤木久志[フジキヒサシ]
1933年、新潟県に生まれる。新潟大学・東北大学大学院修了。文学博士。立教大学名誉教授・帝京大学文学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
げんさん
2
中世史の大家による戦国時代の解説書。中世は天候不順のため、多くの飢饉が発生、それが戦乱の要因になったとの解説。人身売買も広く行われていたようだ
m.murasaki
2
日本中世の危機管理と、奴隷狩りである乱取りを主題とした本。飢饉による身売りの習俗や、貸し渋り対策などなかなか興味深い。大きな災害から復帰するために一つの権力に権限を集中するのでなく広く民間の有力者の力を利用するというのは理にかなった行動なのでしょうね。驚いたのは麦の実りは百姓のものという習俗でしょうか、二毛作で実っても麦は百姓が難儀するので租税として取り上げないとか。さらに戦場での奴隷売買の話ですが、日本もまたあの時代の奴隷貿易のネットワークに取り込まれていたというのは驚きでした。2011/06/24
韓信
1
著者の訃報に接して繙く。日本中世に慢性化していた飢饉と内戦を、民衆はいかにサバイバルしたのかを究明する論考。長雨による寒冷化からの飢饉、そこから発生する土一揆と応仁の乱という戦乱の背景をふまえ、鎌倉幕府による飢饉奴隷許可の時限立法、足利義政や寺社の公共事業による飢饉難民の雇用創出と富の再配分、京都周縁の村人や難民たちによる土一揆の足軽化、武装と自衛の権利を持っていた村、村の傭兵としての穢多、島津氏の豊後侵攻に見られる戦場の奴隷狩りとポルトガル等の奴隷商人との繋がり等々、凄惨な環境とサバイバルの諸相を描く。2019/09/30
お茶
1
保立道久『日本史学』からのおすすめ。まさに今読むべき本。「七度の餓死に遇うとも一度の戦いに遇うな」という諺から始まる日本の内乱の衝撃。内乱の下、飢饉・疫病にあい誘拐・レイプ・奴隷売買される戦国の人々。遠いシリアやイラク・アフガンの内戦の悲惨さを日本も経験していた。決して他人ごとではない、決して加担してはならないと思える本。2015/12/16
k_samukawa
1
良書。戦国時代に興味を持つ大部分の人にとっては「地味な主題」かも知れないが、従前の戦国時代観を一気に塗り替えてしまう可能性を秘めた、興味深い研究の数々。飢饉・奴隷狩りのそれぞれの実例部分だけでも読んで損はない。また、気候変動云々の部分はそのままでは使えないと思うが、文献の悉皆調査も進んでいるし、母群を増やして自然科学的研究と相互補完させればかなりの精度になるのではないかと考える。2011/02/19
-

- 電子書籍
- 別冊NHK100分de名著 集中講義 …
-
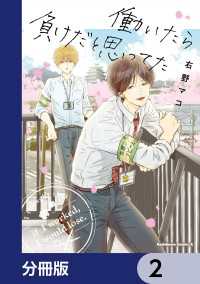
- 電子書籍
- 働いたら負けだと思ってた【分冊版】 2…