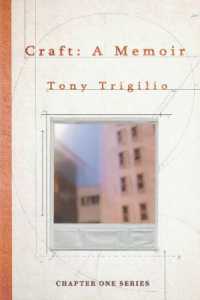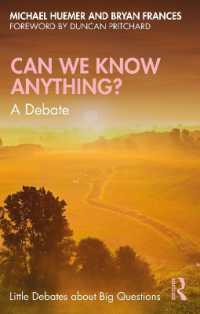内容説明
盃の酒を三口で飲み、それを三度繰り返す三三九度。日本社会では結婚式のみならず、「親子盃」「兄弟盃」「襲名盃」など、約束を固める儀礼として盃事が行われてきた。民俗学者であり現役の神主でもある著者が、ムラ社会の盃事からテキヤ・ヤクザ世界の襲名儀礼に至るまで、フィールドワークと文献を駆使し日本的契約の伝統を探る。小さな盃と酒から見たユニークな日本文化論。
目次
序章 吉備高原上の祭礼
1章 輪島・「お当渡し」の盃
2章 テキヤ社会における盃事
3章 親子盃と兄弟盃
4章 祝言での女夫盃
終章 日本文化としての「盃事」
著者等紹介
神崎宣武[カンザキノリタケ]
1944年、岡山県生まれ。民俗学者。旅の文化研究所所長。故郷の美星町(現井原市)では、家業の神主を務める(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
tama
11
図書館本 著者のファン 盃事で願う・お礼する相手は氏神(社縁)・荒神(地縁)・株神(血縁)・宅神の4柱。神主は盃事の仲介人。高砂・四海波・万葉集が謡われる祭事って出たことないわぁ。この国の信仰は「神様仏様ご先祖様」の三位一体が無理なくてよいね。神仏の世界とのつなぎはご先祖様。ご先祖様に近いのが年寄りたち。議会とかにいる年寄りたちもそうなのかねえ。酒を渡す、それを受けるのはカミが仲介する約束の成立。大事なコメで、一番手間かけて作ったのが酒だから大切なもの。そこは腹の中から同意!!センセ、まあ一献!2020/09/18
にゃん吉
4
輪島市如月祭の「お当渡し」、テキヤの襲名、村社会での親子盃、兄弟盃、婚礼の女夫盃等の日本の盃事を紹介し、霊性のある米に最も手間をかけて作られた酒の神人共食に、盃事の本質を見出し、盃事は、本邦の飲酒文化の精華と力強く結論付ける構成。盃事、ひいては酒礼の衰退を繰り返し慨嘆されていて、著者の飲酒文化への思いが伝わりました。確かに失われゆく文化ですが、ネットで見た限り、趣深い「お当渡し」は今に受継されているようで、安心。式三献の礼講から無礼講の酒席も、メリハリがあって何だか美味しく呑めそうな気がしました。 2019/12/18
takao
2
ふむ2023/05/08
くらた
2
酒と盃で契約を交わす「盃事」は日本の文化ともいうべき契約儀礼。ムラ社会の盃事からヤクザ世界の襲名儀礼まで、様々な例を分析し、その伝統を探っている。こちらも「酒の日本文化」同様、お酒ネタが満載。2009/08/07
tkm66
0
・・宮本常一の学系の筈だが、どーもこの方今一つ②2009/01/12