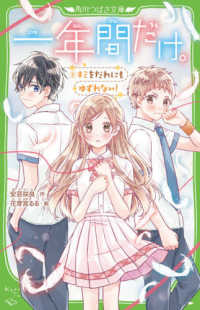内容説明
なぜ親たちは、子どもたちの心を傷つけ、暴力をふるうのか。家庭という密室で進行する子ドもの虐待は、今も深刻度を増している。本書は、沈黙を破って自らの虐待を語り始めた母親たち四人に取材し、その心の軌跡と家庭の闇を描き出した衝撃のルポルタージュ。
目次
第1章 孤立無援の密室(全身アザだらけの幼女;子育てに体罰宣言 ほか)
第2章 凍てた家(おんぶ紐で井戸に宙吊り;「おしん」みたいな嫁 ほか)
第3章 「いい子」役に疲れて(娘を殺してしまいそう;「百日が一山」 ほか)
第4章 波風のない家庭の陰で(問い続ける人生;小さくても母親の世話役 ほか)
第5章 子どもの虐待を考えるために(アメリカの虐待対策は「子どもの最善の利益」が社会合意です;「虐待は家族病理」という正しい認識を持ってもらいたい ほか)
著者等紹介
保坂渉[ホサカワタル]
1954年甲府生まれ。1979年共同通信社入社。現在、同社東京社会部記者
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ジュリアンヌ
6
虐待をしてしまった親を責めてしまう社会意識はどうなんだろう?という疑問をもって読み始めた。虐待をしてしまった親は自分の子ども時代に受容されていなかった経験や、虐待をされた経験、良い子でいることをしいられた…などと不安定な部分を抱えている人が多いことがわかった。さらに、子どもを愛しよう、きちんと子育てをしようという意識を持つお母さんたちが多いこともわかった。親も虐待という家族病理被害者という前提で、虐待をしてしまった親のケアをしていくことが大事だと考えた。2015/07/26
KounoNao
6
虐待を扱った文章というのは、実は当事者にとってはハードルが高いものが多く、どぎつい体験談をつらねてあったりして読み手の不安定さを呼び起こすものが少なくない。けれどこれは、「親」の視点に絞っているせいか、比較的冷静に読みすすめられた。第三者の視点が入る大切さのようなものを感じた。10年前の文章の再録なので内容が古めなのは確かだが、「四面楚歌になっていく私(母親)」がていねいに追われていて、共感ができると思う…その共感が、今のニュースを賑わせる虐待の事件や的外れなコメントに、少しでも影響できないかと、願う。2010/07/03
Ikuto Nagura
5
子どもの人権問題としてしか考えられてこなかった虐待を、「心を病んだ親の問題」と捉え直そうとするルポ。20年程前の実例なのに全く古く感じられないのが、いろんな意味で怖ろしい。本書の4編の母親は、「虐待の連鎖」なる言葉で語られる特殊な人生ではなく、誰にでもあるような生い立ちや人間関係を生きていた。「子どもを虐待してしまう親は、子どもの頃から親や周囲の顔色をうかがい、自分を隠してその欲求に答えようとしてきた人だ」というのなら、現代では寧ろ虐待しない親の方が特殊であろう。さあ、父親としてどう妻子に向き合うかだ…。2016/06/29
emi
4
5章のアメリカの虐待対策は、幾つかは日本でも取り入れて欲しいと思う。斎藤学さんの解説を合わせて読むと分かりやすいが、愛情を受けていない人は愛情の感じ方も鈍い。故に過度に夫からの愛情飢餓感を感じ、その矛先が子供に向く事もあると思う。4章までの四例を読むと虐待が暴力だけではないモノが分かる。むしろ虐待という言葉が普通ではないと身近すぎる事への境界を引いているのかもしれない。子育てが主に女性によるからなのか、虐待というと母の視点でしか描かれない事が多いが、虐待を受けた男性の回復はどのようになされるのだろうか?2011/11/30
-

- 洋書
- DISCIPLINE