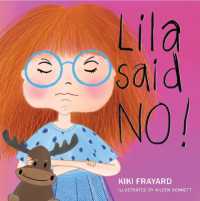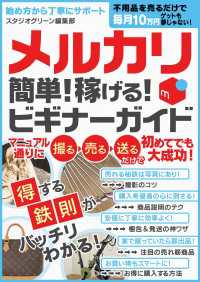出版社内容情報
閉ざされた集団の観念が,抑えのきかない凄惨な暴力をよび起こした.1960年代末,過熱する学生運動の中から誕生した赤軍派.同志粛清,あさま山荘事件へと突き進んでいった政治的党派を社会学の視点から分析した秀作.
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
56
米国の社会学者が日本赤軍を読み解こうとした一冊。主な題材はテルアビブ空港乱射事件と山岳ベース事件なのだが、事件自体に対しては特に目新しい記述はなし。特に興味を惹かれたのは事件後に行った岡本公三へのインタビューだけど、そのままの掲載ではなく著者を通してだから何となく漠とした印象を受ける。あと『菊と刀』的な米国人から見た日本社会論も含まれているが、斯様な閉鎖状況でのエスカレートは洋の東西を問わず起こるのではないかと思ったりした。人民寺院みたいに。とあれ事件について思想的な面からの調査は示唆に富んでいたと思う。2020/10/29
k5
47
シリーズ戦後と平成③。自己批判に総括という異様なロジックの中で、革命を夢見た若者たちが互いに殺し合った背景には何があったのか。丁寧な分析に、アメリカ人の視点からの日本文化論も絡めて解き明かしていくスリリングな一冊です。私の親の世代にとって重要であったイデオロギーという言葉が、私の世代では輝きを失い、人によっては「左翼」という言葉にアレルギーを持つのは、思想の失敗があったと思うのですが、なぜそれが起こったのかというメカニズムについて、改めて思考してみたいと思いました。2025/10/10
富士さん
9
再読。リンチからあさま山荘事件に至る事件の研究のみならず、人間が集団を構成した時独自に発する病理についてのよいケーススタディです。著者が日本的特徴を過剰に探っているのが気になりますが、加害者は被害者への”善意”によっていると考え、被害者は加害者の”善意”を認めて自身への加害者になることで完結する空間はまさに標準的なイジメの構造そのものだと思います。この空間に飲み込まれれば、どんなに強靭な肉体や精神の持ち主でも簡単に壊れることが分かりますし、やはりこの空間を打ち破るれるかは”外部”が重要なのだと分かります。2019/06/03
JunTHR
6
岡本公三へのインタビューから始まり、あさま山荘事件へと至る日本赤軍派、連合赤軍の展開を分析している。特に山岳ベースでの粛清の分析は、場面場面でのかなり細かい心の動きや、集団内での関係の変容などはなかなかに迫力があった。著者はアメリカ人社会学者であり、その視点が活かされるアメリカとの文化的な比較も面白い。日本的なものとして、テルアビブ事件における日本政府による賠償=日本的な連帯責任、山岳ベース事件における屋外への放置=日本的"おしおき"という解釈などは、なかなかなるほどなと。2014/02/08
Ikuto Nagura
5
「革命の獲得目標について曖昧なことしかいえない事実を認めたうえで、岡本はいった。真の目標は、革命それ自体だ。既成権力を世界規模で破壊することだ。その先はわからない」「“総括”をしているとされてはいたが、それが果たしてできるのか、やるべきなのかがわからないのはもちろんのこと、どうやってやったらよいのかまったく見当もつかない状態だった」不明瞭な目的に突っ走るのは、日本人の特性か。「われわれ全員が、連合赤軍事件のような悲劇の、被害者にも加害者にもなりうるのである」著者のたどり着く社会学的な結論に考えさせられる。2014/09/15