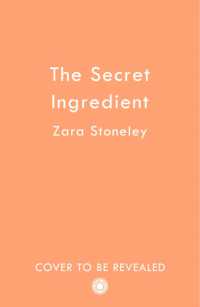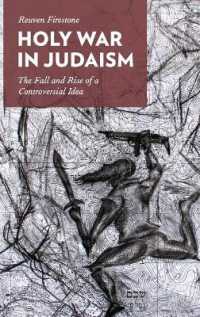出版社内容情報
多彩な人物を登場させ、人物間の葛藤、雄大な合戦場面が次々に展開されるドラマは、読む者を飽きさせない。文豪尾崎士郎の名訳で味わう。
内容説明
『平家物語』は、平清盛を主とした平家一族の全盛から、滅亡に至るまでを描いた軍記物語の代表作。多彩な人物を登場させ、人物間の葛藤、雄大な合戦場面が次々に展開される。琵琶法師により語られた律動感溢れる哀切極まりない名文は、今なお読む者を飽きさせない。『平家物語』を長く愛読してきた文豪の名訳で味わう。下巻には、木曽義仲の侵攻と最期、源義経の平家追討の挙兵、そして壇ノ浦の戦いでの平家の滅亡まで、巻七から巻十二を収める。
著者等紹介
尾崎士郎[オザキシロウ]
1898‐1964年。小説家。愛知県幡豆郡(現西尾市)生まれ。早稲田大学政治科中退、大逆事件の真相解明のため売文社に拠る。高畠素之を追って国家社会主義に身を投じる。1921年に『獄中より』で、小説家として独立する。1933年から「都新聞」に早大生青成瓢吉の人生遍歴を描いた『人生劇場』を連載し、大ベストセラーの長編小説となる(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
❁Lei❁
17
義経が登場する場面のみ再読。以下メモ。九巻「老馬」「坂落し」、十一巻、十二巻「土佐房被切」「判官都落」。お気に入り→「坂落とし」「勝浦合戦」「弓流し」「壇の浦合戦」。十一巻に描かれている屋島の戦いが好きです。決断が早く、時には機嫌を悪くすれども、弓を拾い上げたときににこっと笑う義経、かっこいい。2024/03/30
❁Lei❁
15
義経の活躍を見届けんがため、下巻のみ読了。断崖絶壁からの奇襲を仕掛けた一ノ谷の戦い。逆櫓をつけずに強引に船を進ませた屋島の戦い。舵取を射るという型破りな戦法で活路を開いた壇ノ浦の戦い。その奇想天外な発想と、それを実行してしまう胆力には舌を巻きます。最も盛り上がったのは、雲のように白い旗が飛び、勝敗を分けるイルカが泳いできた場面。天の運はもはや源氏方にあり、義経はますます勢いづいていきます。その陰で倒れていく平家の武将や、入水する女たち。彼らのドラマに心惹かれたのもまた事実で、上巻も読んでみたくなりました。2024/03/12
まこ
13
平家に変わって実権を握る木曾義仲に源義経。彼らにも奢りがあり言動は横暴に。上巻の清盛に比べるとインパクト落ちるなぁ。平家は都落ちの直前辺りから周囲へのやさしさを見せるのが時すでに遅し。最後の徳子の夢は、平家をずっと見てきた読者も含めてのご褒美なのか、平家の奢り体質は変わってないとみるべきか。2021/09/27
α0350α
10
義経の活躍が良いですね。それでも最後は一族が次々と死んでいくので涙無しには読めませんでした。一番驚いたのは解説です。たしかに平家がどんな悪いことをしたのかとか書いてありませんね。2016/09/19
まこ
9
中盤で力をふるった木曽義仲は平家と違い貴族の作法ができていなかった。それが彼が落ちぶれる一つの要因になるあたりまだ貴族の社会な部分が残っている。平家を倒した義経に思い上がりと落ちぶれるフラグがあるけどそこまで描くと終わらないし、「平家物語」ではない。平家の中で最後に残った徳子は中宮時代、天皇の寵愛を受けた相手を追放していたな。最後に彼女のわびしい生活を入れることで前半で平家が落ちぶれさせた人たちのその後と被って見える2020/05/18
-
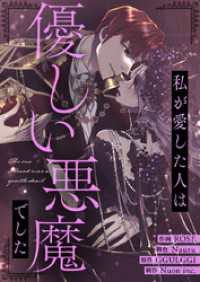
- 電子書籍
- 私が愛した人は優しい悪魔でした【タテヨ…