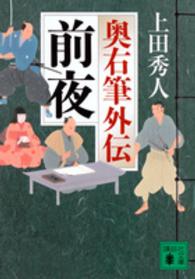内容説明
日常を楽しみ、手紙を交わし、深い信頼で結ばれて青春をともにした明子と蕗子。不治の病を背負った蕗子は、やがて帰らぬ人となった。それから半世紀をへて、蕗子の大切な思い出をまもる明子のまえに、思いもかけない事実が明らかにされる。戦前の昭和を生きた女性の息づかいと秘められた謎を、研ぎすまされた文体で見事に描ききる。全二冊。
著者等紹介
石井桃子[イシイモモコ]
1907年埼玉県浦和に生まれる。日本女子大学校英文学部卒業後、文藝春秋社、新潮社で編集に従事。戦後、宮城県鴬沢で農業・酪農をはじめる。その後、1950‐54年、岩波書店で「岩波少年文庫」「岩波の子どもの本」の企画編集に尽力。一年間の海外留学をへて、荻窪の自宅に私設の図書室「かつら文庫」を開く。長年にわたり児童文学作家、翻訳家として活躍。『ノンちゃん雲に乗る』などの創作のほか、『クマのプーさん』『ちいさいおうち』「うさこちゃん」「ピーターラビット」シリーズなど数多くの翻訳を手がける(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
はる
63
石井桃子さんの自伝的小説。児童文学者としてではなく、一人の女性としての石井さんの姿を見た気がする。上巻の明るさは影を潜め、周囲の人々が次々と倒れる展開は、病気と死からは逃れられない人間の悲哀が漂う。蕗子が送ったという手紙はどれも明るくユーモアに満ちている。だが、その裏に潜む蕗子の孤独な苦しみが哀しい。若くして結核で亡くなった石井さんの親友、小里文子さんへの強い想いが描かせた力作。「くまのプーさん」の和訳はまた、小里文子さんのためでもあった。第四十六回読売文学賞受賞作。2023/11/05
あたびー
35
第二章に至り、明子は慣れぬ結婚生活で悪性の感冒に罹り、蕗子は病状が悪化してサナトリウムに入院、追いかけるように夫節夫の親代わりの叔父が脳梗塞。合間合間に2・26事件まで起こる。第一章ののどかな雰囲気とはガラリと変わってしまう。女二人で仲良く仕立てものや編み物の算段をしたり、バタ焼きの牛肉を食べたり、房総に夏のひと月を過ごしたりしていたあの日々が懐かしい。蕗子の死で戦争の記述なく第二章は終わり、第三章は戦後(恐らく80年代)に飛ぶ。そこで明子は共通の友人佳代子と共に蕗子の真実を追うのだが…2024/11/06
杏子
25
とうとう下巻も読み終わりました。今は虚脱状態… 第一部、第二部通して描かれた蕗子との、たった3年間の友愛に満ちた交流。最後の別れの場面は悲しく寂しくて。第三部で描かれた、その後の何十年間、一度として明子は蕗子のことを忘れたことはなかったでしょう。そこで現れた蕗子の謎も、それを色褪せさせるものではないのです。あえて調べなくてもと思うけれど、それは蕗子のことを何でも知りたいという心がさせたこと。年老い、見送る人を見送っていった明子の思い。身に迫ります。石井さんの数々の翻訳、とりわけクマの物語に思い馳せます。2016/05/16
松本直哉
18
蕗子の衰えと死は、上巻からすでに予期されていたことであってもやはり辛かった。それでも最後まで持ち前の皮肉で陽気なユーモアを忘れず、夫と喧嘩して家出した明子を迎え入れ、入院先の病院ではむしろさばさばとして自らの形見分けを指示する。二二六の雪の朝の緊迫感など、暗い時代も垣間見えるのに、仲良しの二人にとってはもはやどうでもいいことであって、残り少ない生を喜んで全うすることだけが二人の願いだった。長いエピローグで、亡き蕗子の知られざる一面を発見して驚きながらも、哀惜を込めて思い出を語り合う明子と佳代子が心に残る。2025/06/16
わん
8
上巻、若い女性2人の明るく溌剌とした日々から、後半は重く激しくなる。のめり込んで読み、読み終わってちょっと呆然。生きること、死ぬこと、愛すること。あまりにも大きくて、言葉で形取ると、溢れてしまって表し切れないことを、石井さんはこの本で書き上げたのでは…と。読んでよかった。2021/11/12