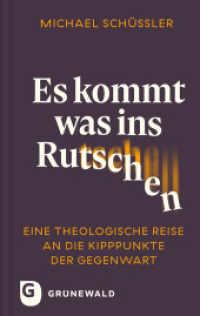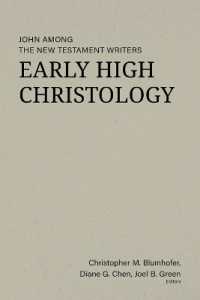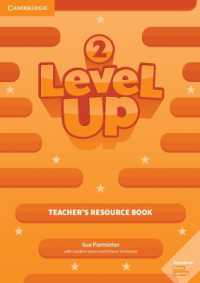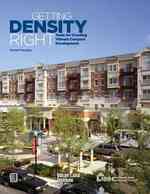内容説明
『蜻蛉日記』は、大政治家の藤原兼家の妻として、波瀾に富んだ生涯を送った道綱母が、その半生を書き綴った王朝女流文学の代表作。結婚生活の苦しみ、夫兼家とその愛人たちへの愛憎の情念が、流麗にして写実的な筆致で描かれる。作品中の和歌は、一段の精彩を放っている。韻文と散文が互いに交響することで、物語に独特の陰翳を与えている。室生犀星の味わい深い現代語訳により、日本古典文学の豊穣な世界に、現代の読者を誘う。
著者等紹介
室生犀星[ムロウサイセイ]
1889‐1962年。石川県金沢市生まれ。詩人・小説家(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
眉毛ごもら
3
蜻蛉日記の現代語訳は無いかなと思って探したらまさかの室生犀星訳だったので購入。道綱母なかなか良い性格してるなと、自分も兼家寝取って独占してた側っぽいのに町の小路の女に寝取られた時に悲しいね🥺って歌を本妻の時姫宛に送っててめえも寝取ったじゃね〜か(# ゚Д゚)と返歌されてたのにはショジョムギョを感じた。リアルツンデレって傍から見てもしんどい感もあり何でこないのよ!来てもツンツンしてるでも来ないの辛い🥺とかしてるのさっさと別れろと思わんでもない。人の色恋はめんどくさい、だからこそファンも多いのだなと思うた2023/09/29
ウラタキ
2
「かげろうの日記遺文」を読んだあとだったので、訳者の文章がするっと入ってきた。この時代の人たちは痴話喧嘩さえ歌でやりあうんだなあ。兼家のことを、とうに飽きたおもちゃを、それでも自分の目に届くところに置いておかないと癇癪を起す子供のように見た。2015/11/07
YY
2
文のやり取りを見てると、なぜに兼家が通うのを受け入れたのかいまいちわからないが、そのわからなさとそれでも通ってこなくなったことへの恨みがましさが変なバランスで、非常に人間臭い。あと、道綱の歌が微妙だったから、振られてもしょうがない、と思った。2014/06/26
卍ザワ
1
清少納言も目標にする程だったという才媛、高階貴子の随筆集。とんぼ、でなく、かげろう日記という。側室なのに、自己主張や承認欲求が強いみたいで、自分でも、己の文才を持て余している印象が窺える。月に数回しか会えない夫にモヤモヤし、自分を日陰者の立場としたり、第三の女の存在にヤキモキしたりとか、精神衛生上あまり、よろしくないだろう、ちょっと湿度高めな日常だった。当時の価値観や、ドロドロとした感情から開放されたら、どういった文学作品を書くのだろうか、と興味深く、思った。2024/04/06
ダージリン
1
道綱の母、の夫が藤原兼家ということも知らなかったぐらいで、全く予備知識をもっていなかった。序盤の歌の応酬にまず戸惑う。ことあるごとに世をはかなみ、何かあれば泣き、全篇こうなのかと呆然となったが、その内テイストにも慣れ、後半はそれなりに楽しめた。兎に角泣いてばかりいる印象は残るが、当時は何かあれば泣くものだったのだろうか?上流貴族の世界はああいう感じだったのか、脚色というか誇張して書いているのか、この時代の知識がなく計り難い。少し勉強してみよう。2018/12/21