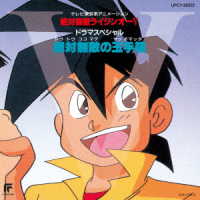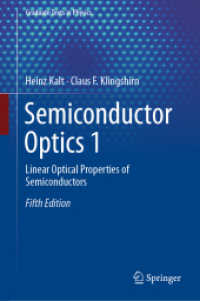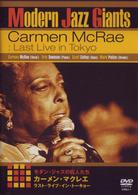内容説明
『モモ』『はてしない物語』など数々の名作児童文学で知られるミヒャエル・エンデが、自らの人生、作品、思索について、翻訳者で友人の田村都志夫氏に亡くなる直前まで語った談話。作品の構想のもととなった、現代の物質文明の行きつく先を見通し、精神世界の重要性を訴えたエンデの深い思想が、語りを通して伝わってくる。各章冒頭、巻末に田村都志夫氏の解説付き。
目次
1 書くということ(言葉、そして名;物語の自律性、そして本という名の冒険;船の難破体験、そしてユーモア ほか)
2 少年時代の思い出(エンデの家系、そして少年時代について;少年時代―馬の話;少年時代―サーカス芸人やピエロのことなど ほか)
3 思索のとき(素潜りする病室の隣人;シュタイナー人智学の芸術観;漢字、身体、そして消える黒衣 ほか)
4 夢について
5 死について
著者等紹介
エンデ,ミヒャエル[エンデ,ミヒャエル][Ende,Michael]
1929‐95年。南ドイツ・ガルミッシュ生まれ。小説家。著書は各国で訳出され、幅広い年齢層に支持されている
田村都志夫[タムラトシオ]
翻訳家。1952年生まれ(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
テツ
24
ミヒャエル・エンデへのインタビュー。『モモ』や『はてしない物語』そして数々の短編からもわかるけれど、物質的ではなく精神的な価値観で世界を眺め、そうした価値観に基づき生きていくことを良しとしているご様子。御自身の創られた物語もそうした思想がベースになっているんだろうな。明らかに不立文字的な、禅的な思考の積み重ねを読み知るにつれて、エンデが日本で(も)好まれて読み継がれている理由が見えた気がします。積み重ねた思考と彼独自の精神世界から生み出される物語をもっと読みたかった。2019/10/28
おだまん
14
エンデさんの著作は音楽のようだと思う。四次元の世界がそこにあるような気がする。環境からもエンデさんやその作品はそうなるべくして形づくられたのでしょう。とても貴重な対談だったと思います。2025/07/25
吟遊
13
エンデの翻訳に携わり、友人でもあった日本人著者によるインタビュー。ほとんどはエンデの語りで構成される。「遊戯」「遊び」(シュピール)についてのエンデ独特の肯定的な視点が面白い。2018/05/29
shoko
7
絵を描くように書くことについて、遊びについて、西洋の価値観と東洋の価値観の違いについて、余白について、戦争について、身体性と精神性について、経済システムについて、死について。面白いところと、ちんぷんかんぷんなところとどちらもあった。/ミヒャエル・エンデは「祖国が第二次世界大戦を起こして敗れた」という原体験からか、異文化を通して祖国を批判的に振り返っており、東洋の文化にも造形が深い。外から見た日本文化の記述も興味深かった。2021/02/07
マネコ
6
モモやはてしない物語を書いた児童文学作家ミヒャエル・エンデへのインタビューをまとめています。 書くこと、少年時代、思索、夢、死について仲の良かった田村さんを聞き手に、物語に色濃く反映された精神的な価値観を感じることができます。 作品が好きな人はもちろん、ジブリや宮沢賢治作品が好きな人にもおすすめです。2019/02/08