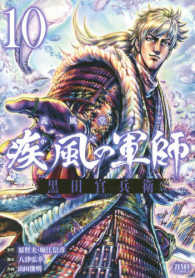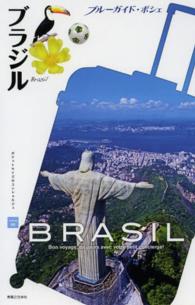内容説明
臨床の現場から生まれた「こころの処方箋」。
目次
1 面接場面の具体的問題
2 クライエントの内的力動
3 クライエント―セラピスト関係
4 セラピストとしての問題
5 治療観から人間観へ
『河合隼雄語録』解題
“解説”読むたびに新しい『語録』のことば
著者等紹介
河合隼雄[カワイハヤオ]
1928‐2007年。臨床心理学者。京都大学理学部卒業。日本初のユング派分析家資格取得。京都大学名誉教授。国際日本文化研究センター所長、文化庁長官を歴任
河合俊雄[カワイトシオ]
1957年生まれ。京都大学大学院教育学研究科博士課程中退。チューリッヒ大学(Ph.D.)。ユング派分析家資格取得。京都大学こころの未来研究センター長(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
ばんだねいっぺい
29
河合先生の本を数多くよんできたが、虎の巻のようなつぶやきが、話しかけてくるように感じる。デンと構えず、相手と自分のこころとこころの揺れをきちんと感じながら、向き合っていくことの大切さを知りました。 2018/06/21
roughfractus02
8
問題解決するのではなく、心身のバランスを取り戻すのがサイコセラピーであると著者はいう。大学院の事例検討会での著者の発言をテープお越しした本書は、専門用語を当てはめて事例を説明するのではなく、臨床の現場で必要なそのつどの処し方を提示しつつ、その根本にある治す/治るのバランスに注力する著者自身の態度を伝える。クライエントの強くなり過ぎた自我を弱めることはセラピスト自身にも当てはまる。臨床における共感とは、言葉の次元で同じ思いになるのではない。身体を持つ者同士が異なる環境にあることを自覚し、思いやることである。2022/12/27
Go Extreme
2
面接場面の具体的問題 クライエントの内的力動 クライエント―セラピスト関係 セラピストとしての問題 治療観から人間観へ 『河合隼雄語録』解題:河合俊雄 読むたびに新しい『語録』のことば:岩宮恵子2021/07/13
🌻さんまり🌻
1
河合隼雄先生が、京都大学の臨床心理学教室で事例検討会を行っていた際のコメントを生徒がノートにしたためており、コピーされ著者没後に生徒の間で読み継がれていたもの。大学院時代に河合隼雄先生の孫弟子から指導を受けていたわたしにとっては、心にストンと落ちることばだらけの一冊。あの河合先生が「我々凡人としては」なんて仰るわけなんだから、凡人として人と接していこうと思います。あと、余談だけど「いいのと違うかな。」みたいかことばの使い回しが、個人的にとても好きです。2019/06/07
saiikitogohu
0
「その人が荷物を背負えるところまでは、こっちはその人を強くするほうに回らなきゃいけない」17「自分は本当にダメな母親です…何か向こうも口先みたいだし…仕事でどんなことしてますか、のか、…結局そういう風にこの人が人間としてがんばっているということを僕が認めているということを作る方が先ですね。…弱い人ほど周辺から固めなきゃいけないわけでしょ」19「過保護の家っていうのは、だいたい愛情が不足していると思う」45「非常に深いレベルでフーンという」482020/07/11