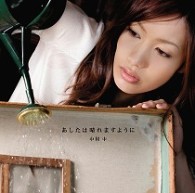出版社内容情報
白紙に残された表象の痕跡、絵画の二次元、スクリーンに投射される光の運動……。様々な芸術ジャンルを横断しつつ,20世紀の思考風景を決定した表象空間の政治学を明るみに出すチャレンジングな論考。解説、島田雅彦氏。
内容説明
近代的イメージは、いつ、いかにして出現したのか―。一八八〇年代以後の西欧に出現した映画、ファシズム、精神分析という「イメージ」の政治にかかわる二〇世紀的な「装置」を手掛かりに、絵画の二次元やスクリーンに投射される光の運動などの、前世紀の表象空間の特質を明るみに出す。
目次
表象空間の地滑り
1(「蝟集空間」;「無人空間」;“像”と“貌”;「現実的なるもの」をめぐって)
2(“枠”あるいは「イメージ」の自意識;鋳型・骰子・ページ;辱められた黄金;“面”あるいは「イメージ」の「場なき場」)
3(“面”から“幕”へ;時間の断面;鏡と幽霊;“幕”あるいは反=ナルシスの装置)
「平面」と「近代」
著者等紹介
松浦寿輝[マツウラヒサキ]
1954年東京生まれ。作家・詩人・仏文学者・批評家。東京大学名誉教授。東京大学大学院仏語仏文学専攻修士課程修了。パリ第3大学にて博士号(文学)を、東京大学にて博士号(学術)を取得。詩集に『冬の本』(高見順賞)、『吃水都市』(萩原朔太郎賞)、『afterward』(鮎川信夫賞)、小説に『花腐し』(芥川龍之介賞)、『半島』(読売文学賞)、『名誉と恍惚』(谷崎潤一郎賞)、エッセー・評論に『折口信夫論』(三島由紀夫賞)、『エッフェル塔試論』(吉田秀和賞)、『知の庭園 一九世紀パリの空間装置』(芸術選奨文部大臣賞)、『明治の表象空間』(毎日芸術賞特別賞)など多数(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
gorgeanalogue
古義人
きくらげ
岡部淳太郎
シン
-

- 洋書電子書籍
-
医療過誤の物語:医者の必要な失敗