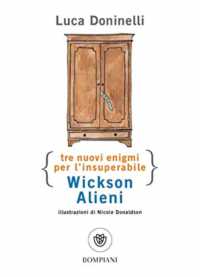内容説明
原始仏典のなかでもっとも有名な「法句経(ダンマパダ)」、ブッダの弟子である僧・尼僧の告白「テーラガーター」「テーリーガーター」、在家信者の心得を説いた「シンガーラへの教え」など初期仏教の清新な勢いを感じさせる重要な経典を、仏教学の泰斗がわかりやすく解説。また、仏教王アショーカの岩石詔勅、ギリシア人の王と高僧との討論として名高い「ミリンダ王の問い」も解説。NHKラジオで大好評を博した名講義を活字化した「お経」入門シリーズ第二巻。
目次
第6回 真理のことば―『ダンマパダ』(『法句経』)
第7回 仏弟子の告白・尼僧の告白―『テーラガーター』・『テーリーガーター』
第8回 人間関係―『シンガーラへの教え』(1)
第9回 生きていく道―『シンガーラへの教え』(2)
第10回 アショーカ王のことば―岩石詔勅
第11回 ギリシア思想との対決―『ミリンダ王の問い』
著者等紹介
中村元[ナカムラハジメ]
1912‐99年。東京帝国大学文学部印度哲学梵文学科卒業。東京大学名誉教授。東方研究会・東方学院を創設。日本学士院会員・文化勲章・勲一等瑞宝章受章
前田專學[マエダセンガク]
1931年生まれ。東京大学文学部印度哲学梵文学科卒業。東京大学名誉教授。日本学士院賞受賞。東方学院長として活動(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ホシ
15
中村先生のお人柄が滲み出るかのような本。「ダンマパダ」「テーラガーター」「テーリーガーター」「シンガーラの教え」"岩石詔勅"「ミリンダ王の問い」計5つの初期仏教経典をやさしく中村先生が解説します。初期仏教経典の入門書として格好の良書です。私たちの生き方の指針となるばかりでなく、不穏な空気漂う現代世界の情勢に照らし合わせて見ても、これら5つは非常に示唆に富むものと思います。特にアショーカ王については勉強になった!いいヤツだなアショーカ!!2018/05/13
roughfractus02
8
死後、ブッダは創始者として物語の中に移動する。その際、真理の意味は二重になる。ブッダが話した言葉の真理は理法(ダルマ)だったが、彼の死後言葉は人々の声の記憶となり、他者の声を介してブッダ自身の言葉という新たな真理が現れる。本書は、修行前の苦しみとブッダに帰依して安住を得た下層の者達のエピソードを語る長老の詩と心の安住を得るための心得、さらに仏教を保護したアショーカ王が嘆じた戦争の残酷さやギリシャのミランダ王と対話するナーガセーナの物語によって、初期仏教が古代インドのカースト社会を超えて広がる様を示唆する。2021/04/15
Kooheysan
6
原始仏典のいいとこ取り第2弾。『ダンマパダ』などを扱っています。第1弾もそうですが、原始仏典のエッセンスに気軽に触れることができるのは有難いです。原文引用後の解説がまさに自分が欲しかった説明ぴったりなのがある意味驚くほどです。「自己はじつに制し難い」…人間はいつの世も変わらないのですね。アショーカ王の岩石詔勅に刻まれていた宗教への姿勢が素敵です。そしてこの後、原始仏典の教えがどのようにして大乗仏典へと変化していくのか、興味深いところです。2025/07/13
Hiroshi
4
原始仏教典の ①ダンマパダ、②テーラガーター・テーリーガーター、③シンガーラへの教え、④アショーカ王の岩石詔勅、⑤ミリンダ王の問いについて書かれている。大乗仏教の日本では余り見ない経典だ。①は具体的で簡単に書いてある。同じ行為でも、その人の心が清らかか否かで意義が違ってくる。良い行いは、他の人々に何らかの形で働きを及ぼし残ると。恨みを抱くと、その連鎖が続く限りお互いに恨み続けると。②は仏弟子・尼僧の告白だ。一族が滅びた女性は八正道を実践して安らぎを現に悟り、真理の鏡をみた。最高地位にいた遊女の没落の話も。2018/05/02
えふのらん
3
ブッダの生涯に続く本で概念的なことに焦点が定められている。唯識的な疑惑、四苦と四諦、そういった人生の影の部分を脇見しながら涅槃へと読者を誘う。生涯篇に引き続いて用語を用いた議論はないが、仏教が目指しているものが何となくわかるように書かれている。あと本書の白眉はテーラガーターとミリンダ王の問いの抜粋で、これらのおかげで大乗仏教以前の教団のイメージを掴む事ができた。仏教入門といばことばと真理だが、そういった教義以上のものを得ることができる。2022/08/14