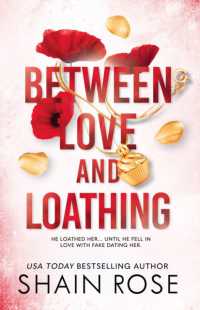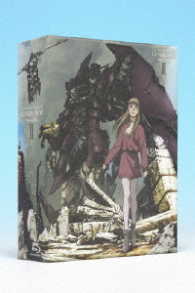出版社内容情報
レヴィナスが問題とした「時間」「所有」「他者」とは何か? 難解といわれる二つの主著のテクストを丹念に読み解いた著者初期の名著.
内容説明
戦争と虐殺の世紀を生き延び、さまざまな「無用の苦しみ」を問うことから生じたレヴィナスの哲学。そのテクストに刻み込まれた「時間」「所有」「存在」「他者」とは何を意味するのか。倫理学の第一人者である著者が、難解といわれる二つの主著『全体性と無限』『存在するとはべつのしかたで』のテクストを緻密に読み解く。現代を生き抜く強靭な思考を浮かび上がらせる名著。
目次
第1部 所有することのかなたへ―レヴィナスにおける“倫理”をめぐって(問題の設定―“身”のおきどころのなさの感覚から;自然の贈与―始原的な世界を“口”であじわうこと;所有と労働―世界に対して“手”で働きかけること;裸形の他者―“肌”の傷つきやすさと脆さについて;歴史の断絶―声ではない声に“耳”を澄ませること)
第2部 移ろいゆくものへの視線―レヴィナスにおける“時間”をめぐって(はじめに―移ろいゆくものへ;物語の時間/断絶する時間;時間と存在/感受性の次元;主体の綻び/反転する時間;おわりに―“ある”への回帰)
著者等紹介
熊野純彦[クマノスミヒコ]
1958年神奈川県生まれ。東京大学文学部卒、現在、東京大学文学部教授。倫理学・哲学史専攻(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
踊る猫
31
熊野純彦の姿勢はストイックだ。他の批評家・哲学者の言葉を全くと言って良いほど引用・参照せずに、エマニュエル・レヴィナスの言葉/テクストに触れてそこからエッセンスを抽出しようと試みている。だから悪く言ってしまえば熊野がレヴィナスをダシに自分を語った本、閉じられた本と解釈することも出来る。だが、真摯な姿勢をそう意地悪く解釈したくない。『レヴィナス入門』と並んで初学の人間がレヴィナス哲学に触れるためには必須の本として推したい。そして、ここからどう思考を広げるか。熊野の他の著書を読むか倫理学を読むか。それは自由だ2018/09/19
踊る猫
30
本書において熊野は実に素朴な問いを幾度となく問いかける。「他者」とは誰か、「世界」とはなにか。そうしたあまりにも原初的な問いかけを実践することを通じて、熊野はレヴィナスの思考の根底にある可能性を探り出そうとしていると思った。あくまでぼくのつたない読解を断っておくが、そうした可能性とはつまりレヴィナスが語らんとしたものがいかに「実際的」「現実的」にそこにいる他者あるいは裸形の世界そのもの、そしてそうした世界の中で自分自身が「ある(存在する)」ということなんだろうかと。難解な観念論ではなく「使う」ための1冊だ2024/09/13
しんすけ
6
<私>が<他人>の心の内を観ることは叶わない。だがそれでも現在まで、社会は成立し存続している。それは人間の体験がロゴスによって共有されるからであろう。ロゴスに寄与するものとして感覚が注目されることは多い。 熊野は特に嗅覚に注目し下記のように語る。 /嗅覚そのものには、もうひとつの両義性がある。嗅覚は「へだたった味覚」であり、しかし味覚とことなって意思に反しても「享受」(genießen)される。...臭いはあたりにたちまち拡散し、いつまでも漂うこともある。2019/02/23
くまさん
5
まばゆいばかりのレヴィナスのモチーフが詳細に吟味されていく。始原世界の享受、所有や労働や住まいの連関、他者の〈顔〉がもたらす殺人の禁止等々。現に殺人が「日常的」に行われているのに、殺人の不可能性が語られる意味は、他者の絶対的な他性そのものを抹消することがどこまでもできないことにある。他者との関係のなかで自分は逃れようもなく「責め」を負い、ひとたび応答したかぎりはその圏内にとらわれる。だが、そこに倫理のかたちとありかがあるのだろう。言葉が贈与であり願いをこめた呼びかけであり、誰かに届くことの奇跡を想う。 2018/01/11
午後
4
レヴィナスの断言的なテクストの空隙に潜り込み、そこに充満している論理を掬い出す手つきの鮮やかさと粘り強さに感動すら覚えた。始原的なものの享受、労働と所有、道具とすみかなど、『全体性と無限』を所有の観点から読み直す第一部が面白かった。第二部は難しくてわからなかった。2022/07/12
-
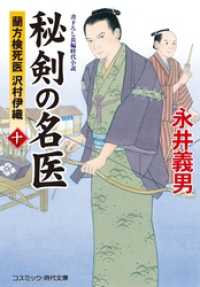
- 電子書籍
- 秘剣の名医 十 蘭方検死医 沢村伊織 …