出版社内容情報
自由」や「リベラリズム」を論じるには「自由の秩序」を考えなくてはならない。法哲学の第一人者が講義形式でわかりやすく解説。
内容説明
リベラリズムや自由が危機に瀕しているといわれるいま、「自由」とは何かを理解するためには自由を可能にする原理と制度構想を考えなくてはならない、という立場から著者は「自由の秩序」について講義する。「自由」や「リベラリズム」の法哲学的意味とは何か?「自由」と「正義」との関わりとは?井上教授の熱血講義に対し、聴講生たちが具体的な事例も交えた鋭い質問で迫る、対話形式の刺激的な議論も収載。
目次
第1日 アルバニアは英国より自由か
第2日 自由の秩序性と両義性
第3日 自由概念の袋小路
第4日 秩序のトゥリアーデ―国家・市場・共同体
第5日 専制のトゥリアーデ―全体主義的専制・資本主義的専制・共同体主義的専制
第6日 自由の秩序の相対性と普遍性
第7日 世界秩序をめぐる討議
場外補講 リベラリズムにおける自由と正義の位置
著者等紹介
井上達夫[イノウエタツオ]
1954年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専攻は法哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
takeapple
10
自由と秩序ではなく、自由の秩序と言うところがミソで、2つは対立するものではなく、自由の実現のためには、秩序が不可欠と言うことだ。井上先生の本なので難しいけれど、なるほどなあと思わせる。しかしアナキズムについても言及されているとは!と最初驚いたけれど、自由と秩序の本なんだからある意味当然かなあ。7日目と番外編がとっても面白い🤣2022/01/25
ころこ
8
本書は講義形式ですが、かなり堅めの政治哲学本です。本講義では、テイラーの質的自由概念や、バーリンの消極的自由と消極的自由の区別を批判し、自らは国家、市場、共同体からなる、秩序のトゥリアーデを提唱しています。場外補講の残り3分の1で、秩序のトゥリアーデは自由の保障手段に関わっているだけで、保障すべき自由の中身には迫っていないという本丸の議論に批判が向けられる体裁になっています。そこで、著者はリベラリズムの説明を行います。本書の論点は、秩序のトゥリアーデとリベラリズムということになります。正義概念がリベラリズ2017/06/29
フクロウ
2
個人の自由というものもいきなり天から降ってくるわけではなく、それを支える秩序が必要である、という話自体は、たとえば小林正弥や、岡田与好、樋口陽一らも指摘していたところであり、(井上達夫の指摘が彼らより先か、後かはわからないが)。/反転可能性は視点の反転も含むから、「自分がユダヤ人なら喜んで絶滅収容所に入る」と言うナチス将校は、(真摯なものだとしても)実は反転できていないという話はなるほどと思った。2024/05/06
ホリエッティ
2
p.51「国家は単なる暴力装置ではありません。自己の暴力行使の合法性担保にコミットし、自己の支配下の諸個人を保護する責任を引き受けた暴力装置なのです。」2024/01/03
馬咲
2
薄めの本だが、著者の法哲学のエッセンスが豊富で、情報量は多い。自由の秩序はその根本理念として「正義」を据えている。それにより諸個人の自由それ自体は擁護しつつ、自由の行使による行為内容については、普遍的正義理念の要請の下、行為者が自己を他者の視点・状況に徹底的に肉薄させた上で当該行為をなお受容可能か吟味する倫理的判定テストの責務を各自に課す。他者への眼差し、倫理的構想力を欠き、自由を放縦と履き違える凶暴な自己中心性の徹底的な排除が狙いだ。従来の自由概念の危うさについての指摘は鋭く、そのリベラリズムは逞しい。2022/11/04
-

- 電子書籍
- 【単話】チュートリアルが始まる前に ボ…
-
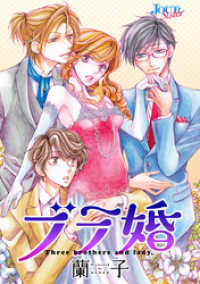
- 電子書籍
- ブラ婚 分冊版 7話 ジュールコミックス







