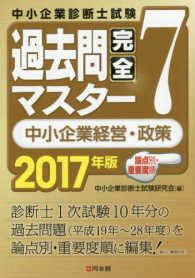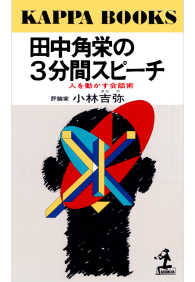内容説明
和食とともに再び熱い注目を集める日本文化の粋、日本酒。江戸初期にはほぼ確立されていた酒づくりの技術は、その後三百年の間にさらに洗練され磨き上げられた。杜氏らによる品質改善の試行錯誤、幕府統制下での酒屋の生き残り戦略、外国人が見た日本の酒事情など、江戸時代の日本酒をめぐる歴史・社会・文化を、史料を読み解きながら精細に描き出す。
目次
第1章 花の田舎の酒―京都の近世酒づくり
第2章 酒づくりの技術―職人技の極致
第3章 酒造統制と酒屋の盛衰―制限と緩和の間で
第4章 東北諸藩の酒づくり―鉱山町・寒冷地の酒
第5章 御免関東上酒―下り酒に負けない酒を
第6章 外国人の見た日本酒―つくり方と味をめぐって
著者等紹介
吉田元[ヨシダハジメ]
1947年京都市生まれ。京都大学農学部卒業、農学博士(京都大学)。種智院大学名誉教授。専門は発酵醸造学、食文化史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
本命@ふまにたす
4
近世日本における「酒」について書かれた一冊。コンパクトな本ではあるが、酒造技術からヨーロッパ人が見た日本の酒についてまで、複数の観点から考察が行われており、普段飲酒しない人間にとっても興味深い内容。2022/10/17
飯田一史
1
原料に大量の米を消費する酒造業は食料と競合せざるをえない宿命にあった。天候や経済状況、幕府の統制策に翻弄されながら有り様を変え、京都から全国へ広がっていった日本酒の近世史。2020/01/14
55くまごろう
1
江戸の酒と言いつつ、内容的には江戸の話はごく一部で江戸時代の日本酒の政治や社会との関係性を中心とした話である。そうであることは前書きにも明確に記載されており、それで良いと思うし、内容的にも他ではなかなか知ることのできない貴重なものであった。日本酒に対する総合的な知識の一つとして、役立つと思う。2020/01/08
もけうに
1
内容は興味深いのに、全体的に散漫として纏まりが無いのが残念。著者の文章力もイマイチ。2019/05/14