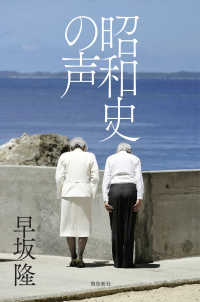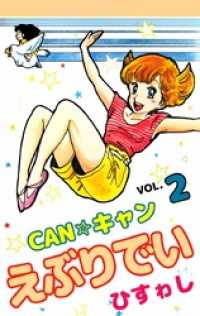内容説明
私たちの生を包む諸関係は、深刻な病理を抱えているのではないか。象徴天皇制が象徴する「関係の貧困」、会社主義が具現する「共同性の貧困」、五五年体制の遺産たるコンセンサス原理が孕む「合意の貧困」、この三つの病因から、日本社会を構造的に診断。リベラリズムに基づく社会の再編へむけて、ラディカルな思想的処方箋を描く。
目次
第1部 関係の貧困(天皇制を問う視角―民主主義の限界とリベラリズム;付論 補足と解題―天皇制・民主主義・リベラリズム)
第2部 共同性の貧困(個人権と共同性―「悩める経済大国」の倫理的再編)
第3部 合意の貧困(合意を疑う;政治的知性の蘇生に向けて;コンセンサス社会の危機と変革)
著者等紹介
井上達夫[イノウエタツオ]
1954年生まれ。東京大学法学部卒業。現在、東京大学大学院法学政治学研究科教授。専攻・法哲学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件