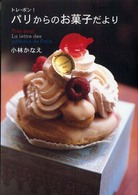出版社内容情報
無文字社会の歴史を探究することは,文字社会を相対化する視点を築くことに通ずる.西アフリカ・モシ族を調査し,音の世界や儀礼から無文字社会の性格を見事に分析した本書は,日本の文化人類学の記念すべき達成である.
内容説明
無文字社会の歴史のあり方を探究することは、人類文化における文字社会を相対化する視点を築くことに通ずる。一九六〇年代から七〇年代前半に西アフリカ・モシ族を現地調査し、太鼓ことばを含む口頭伝承や儀礼などから無文字社会の歴史と構造を鮮やかに分析した本書は、日本の文化人類学の記念すべき達成である。
目次
非文字史料の一般的性格
文字記録と口頭伝承
モシ族の場合
系譜の併合
絶対年代の問題
歴史の始点
反復する主題
口頭伝承の定型化
首長位の継承
歴史伝承と社会・政治組織
イデオロギー表現としての歴史伝承
歴史伝承の比較
制度の比較
発展段階の問題
「伝承的」社会という虚像
神話としての歴史・年表としての歴史
文字と社会
おわりに
著者等紹介
川田順造[カワダジュンゾウ]
1934年東京生まれ。58年東京大学教養学部卒業。パリ第五大学(ソルボンヌ)で民族学博士。東京外国語大学アジア・アフリカ研究所教授を経て、広島市立大学国際学部教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
サアベドラ
15
西アフリカの現在のブルキナ・ファソにあたる地域に住むモシ人の口承史の分析により、無文字社会における歴史のあり方と社会との関わりを考察する。著者は西アフリカでの十数年のフィールドワークののちソルボンヌで博士号を取得した文化人類学者。本書の初出は1976年。見慣れない地名や人名が大量に出てきて読むの少々苦労したが、口承史の現在性、文字社会における無文字性などいずれも興味深い内容ばかりだった。途中で西欧中心の民族学・文化人類学の有り様を強く批判している箇所があるが、まあ執筆当時はそういう時代だったのだろう。2013/12/10
Mentyu
5
筆者によるモシ族の歴史研究は口碑や伝承の聞き取りで行われるのだけど、それが日本古代史の研究方法とそっくりで驚いた。特に王の系譜を整理するやり方は、記紀に残された大王の系譜を研究する手法とほとんど変わらないという。本の終わりでは文字社会と無文字社会の比較についての言及があるのだけど、そこは打って変わってメディア論のようになっていて、どこかマクルーハンの議論を髣髴させるものだった。2017/11/28
たま
1
レヴィストロース嫌いなんかな?(古い本だけど面白かった)2019/04/27
AR読書記録
0
タイトルからは,無文字社会において,“歴史”はどう伝えられてきたかとか,それを研究者がどう解読し裏付けていったか,という,スリリングな謎解きみたいなのを想像して読んでしまいました.が,そういうパートはそう多くはなくて,もっと引いたところから,いったい文字は社会においてどういう存在なのかとか,あるいは欧米視点による人類学批判とか,研究者のありようみたいなところを伝えることに,重点があった気がします.分野を問わず“研究”を志す人の基本テキストとなりうるレベルの.読み応えあった.2012/05/23
★★★★★
0
懐かしい
-

- 和書
- 図解気相合成ダイヤモンド