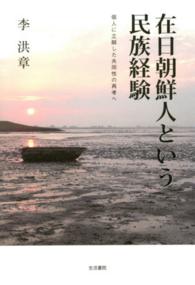内容説明
母親の胸に顔を埋め、無心に唇を吸い続ける赤ん坊、スナイパーの銃撃におびえながら熱い抱擁を交わして愛を確かめ合う若い恋人たち、自爆攻撃をした「英雄」の息子の遺影を複雑な表情で抱える父親…。貧困、飢餓、民族対立のなかで「死」と隣り合わせに暮らす人々の「生」を撮り続けたフォトグラファーが生きることの意味を問う。
目次
ソマリア―1992年
ボスニア・ヘルツェゴビナ―1994年
南アフリカ―1994年
ルワンダ―1994年
シエラレオネ、リベリア―1996年
アフガニスタン―2001年
パレスチナ―2002年
南スーダン―2003年
カンボジア―2006年
飯舘村―2011年~
著者等紹介
橋本昇[ハシモトノボル]
30年にわたり、フランスの写真通信社Sygma(現在はGetty Images)の契約フォトグラファーとして、国内の被災地や海外の内戦、難民を取材(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
kinkin
105
写真家である著者が9つの国の内戦地を巡った時のルポルタージュ。ソマリア、ボスニア、南アフリカ、ルワンダ、シエラレオネ、アフガニスタン、パレスチナ、南スーダン、カンボジア。どの国の内戦もニュースや新聞では聞いたことがある。しかしその情報はこま切れで結局どんな状態だったのかわからないままだった。なぜ同じ国道死の国民傷つけあい殺し合うのか?と考えたとき日本も戦国時代は日本のあちこちで武力争いもあったのだから偉そうに言えないか。載っている写真はどれも見るものを悲しくさせる。「いのち」を感じてほしい本。図書館本 2022/03/01
井月 奎(いづき けい)
43
内戦による混乱に翻弄される人々の様子を教えてくれます。(内戦の地とあるこの本に原発事故によって苦しめられている福島、飯舘村を選んでいる著者の思いは一考すべきでしょう) 遠い地や過去であっても、内戦に苦しめられる無辜の民の様子を知ることは罪悪感を含む痛みをもたらせます。 なぜ罪悪感を抱くのでしょう? それはこの悲劇、混乱を生み出したのが人の知だからではないでしょうか?しかし同時にその資質は人の笑顔を生み出す資質でもあるはずなのです。わずかでもそちらに向かうようにしたいと願い、本を閉じました。 2020/07/23
榊原 香織
22
う~ん、読んでてうめいてしまいました。 各地の内戦30年の記録なのでやや平和になったところもあるけど。 アフリカ多いなあやっぱり。岩波ジュニア新書大好き #推薦本2020/09/11
アナーキー靴下
8
内戦が起きた様々な国の状況や著者の体験が、いくつかの写真と簡単な経緯付きで紹介されている。岩波ジュニア新書、ということもあり、子供から大人まで幅広くおすすめできる本だと思う。(漢字のルビは少ないので、小学生だと読みづらいかも?)シエラレオネ、リベリアの話はほとんど知らなかったし、他の国もその後どうなったかを把握していない部分もあったため、今読んでよかった。著者の「命の詩」という表現は、人間の醜さや残酷さといった部分以外にも目を向けてきたからこその言葉だと感じた。2020/08/08
むさみか
4
ちんまりと一包みになってしまった 幼児の遺体など 胸を突かれるものがあります 実際に現地の様子なども克明に綴られ 内戦状態の悲惨な真実を 伝えてくれています 分かれば分かるほど 人と人がいがみ合うことの虚しさに 気が付かせてくれます2019/06/24