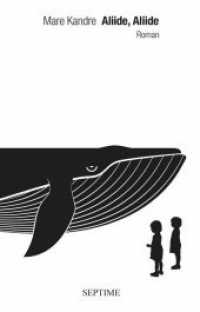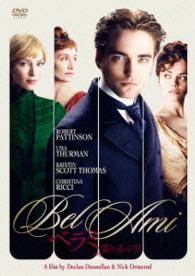出版社内容情報
明治という時代は実はとても厳しい社会でした。景気の急激な変動、立身出世競争、貧困…、さまざまな困難のなか、人々はこの時代をどう生きたのでしょうか? 不安と競争をキーワードに明治社会を読み解きます。
内容説明
日本が近代化に向けて大きな一歩を踏み出した明治時代は実はとても厳しい社会でした。景気の急激な変動、出世競争、貧困…。さまざまな困難と向き合いながら、人々はこの時代をどう生きたのでしょうか?不安と競争をキーワードに、明治という社会を読み解きます。
目次
第1章 突然景気が悪くなる―松方デフレと負債農民騒擾
第2章 その日暮らしの人びと―都市下層社会
第3章 貧困者への冷たい視線―恤救規則
第4章 小さな政府と努力する人びと―通俗道徳
第5章 競争する人びと―立身出世
第6章 「家」に働かされる―娼妓・女工・農家の女性
第7章 暴れる若い男性たち―日露戦争後の都市民衆騒擾
おわりに―現代と明治のあいだ
著者等紹介
松沢裕作[マツザワユウサク]
1976年東京都生まれ。1999年東京大学文学部卒業、2002年同大学院人文社会系研究科博士課程中途退学。東京大学史料編纂所助教、専修大学経済学部准教授を経て、慶應義塾大学経済学部准教授。専門は日本近代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
mukimi
113
親孝行すべしとか節約し勤勉に働くべしとか日本人の骨の髄まで染み込んだ通俗道徳は、国民の信頼を勝ち得るには真新しすぎた明治政府が身を守るのに都合の良いものであった。国民は生活が上手くいかなくても国を責めず自ら(や努力出来ない弱者)を責めるからだ。これは令和の私たちにも通じるだろう。生きづらさの源流が自らの内にあるのか外にあるのか、自らの信条は誰かの都合の良いように整形されてはいないか、慎重に吟味せねばならない。正義を疑う、そんなことをこのジュニア新書を読む小中学生が知りながら大人になっていけるのは羨ましい。2024/09/15
venturingbeyond
83
地元書店で、ジュニア新書フェアが開催されており、平積みになっていた本書を購入。明治期の激変する社会の中で、「通俗道徳」に縛られた民衆がいかに厳しい生活を過していたのかを、ジュニア新書の想定読者を意識した平易な文体で簡潔に叙述。高校の日本史では、後景に引いてしまっている民衆史であるが、このような著作を読んで、明治史を重層的に理解してもらいたいところ。特に、6・7章は現役高校生にお薦め。2021/08/01
ちくわ
78
江戸時代⇒明治時代…日本史上の大転換点であった事は多くの共通認識だろう。ただ文明開化で表現されるように明るい印象が強く、陰の部分をあまり知らない。歴史は両側面から見るのも大事なので読んでみる事に。 感想…明治の暗い陰は知れたが、何か違和感があるんだよな。その違和感の正体は題名…ちょっと主語が大き過ぎない? 生きづらい人『も』いた…が正解で、国民の誰もが生きづらかった訳ではないだろう。著者の左翼思想が溢れ出たのかな? 歴史の評価に絶対も不変も無いので、令和も後に意外と高く評価される可能性もゼロじゃないよね。2024/10/02
kei-zu
78
明治時代となれば、世の印象は「坂の上の雲」なのだろうか。だが本書は、明治を「不安と競争の時代」であったと説明する。社会の構造が変わる中、個人を支える仕組みは旧態依然のままであった。それにしても、「自己責任」を謳うのがこの時代からだったとは。 現代社会との類似も挙げながらも、その背景にある「変わったこと」「変わっていないこと」の比較が興味深い。 であれば、これからの時代を私たちはどのように変えていけることができるだろうかと思う。2023/01/06
yomineko@💖ヴィタリにゃん💗
70
ゴールデンカムイで興味を持った明治時代、、、しかしそこは人が暮らしにくい、特に女性が暮らしにくい社会があって中々改正されなかった。お金のために売られる女性達。。。人権などない様なものだった社会で生きて行った人々を赤裸々に描いているのですが、ジュニア新書にしては難解な漢字が多すぎます💦2021/12/09