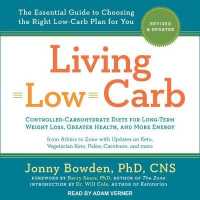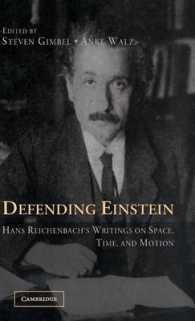内容説明
文化立国フランスを彩る数々の宝刀の中でも、ひときわ輝きを放ち、世界の人々を甘く魅了してきた「お菓子」。それは教会や修道院で生まれ、やがて王や貴婦人たち、そしてブルジョワや文豪、パティシエたちによって、戦略的に磨かれてきた。フランスの歴史をその結晶であるお菓子によってたどり、フランスの「精髄」に迫る。大人気!!東大講義。「パスタでたどるイタリア史」につづく第2弾!
目次
序章 お菓子とフランスの深い関係
第1章 キリスト教信仰と中世の素朴なお菓子
第2章 略取の名手フランス
第3章 絶対王政の華麗なるデザート
第4章 革命が生んだ綺羅星のごとき菓子職人
第5章 ブルジョワの快楽
第6章 フランスの現代とお菓子
著者等紹介
池上俊一[イケガミシュンイチ]
1956年、愛知県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科教授。専門は西洋中世・ルネサンス史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
-
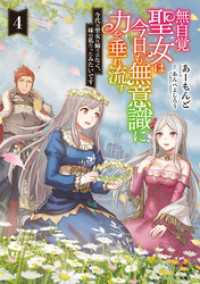
- 電子書籍
- 無自覚聖女は今日も無意識に力を垂れ流す…