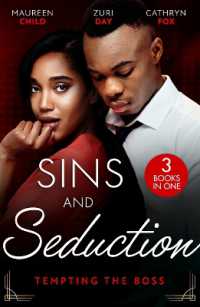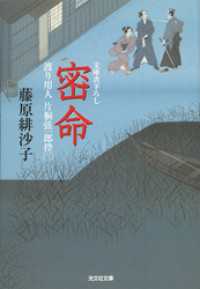出版社内容情報
地球上の資源は無限にあるわけではありません.今を生きる私たちは,限りある資源を偏りなくいかに分配するかということが問われています.「効率」「衡平」「公平」という考え方をカギに,人の福祉にとって望ましい社会のルール,経済システムのあり方について論じます.
内容説明
経済のグローバル化、人口の高齢化、地球環境問題など、さまざまな課題を抱える現代社会…。私たちは今後、どう生きていくべきなのでしょうか。「効率」と「衡平」をキーワードに、ひとの福祉とは何か、人々の福祉を高めるために望ましい社会経済システムとはどのようなものなのかを考えます。
目次
1 経済とは?
2 ひとの福祉とは?
3 無駄のない経済システムとは?―効率性の考え方
4 市場システムの効率性
5 格差のない社会とは?―衡平性の考え方
6 消費・労働に関する衡平性―無羨望配分の考え方
7 消費・労働に関する衡平性―平等等価の考え方
8 機能に関する衡平性
9 経済学の役割
10 さらに学びたいひとのために
著者等紹介
蓼沼宏一[タデヌマコウイチ]
一橋大学大学院経済学研究科教授。専門は社会的選択理論、厚生経済学、ゲーム理論。1982年、一橋大学経済学部卒業。84年、一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了。89年、ロチェスター大学大学院経済学博士課程修了、Ph.D.(in Economics)取得(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
1.3manen
9
happiness economicsが出てきたことで社会的にも普及しつつある本の一つ。経済は福祉を高めるためにある(8頁)。幸福はJ.ベンサム以来の効用(41頁)。A.センの潜在能力は健康や人権も関わる(47頁)。選択の機会の自由(152頁)。かけがえのない権利であろう。J.ロールズの格差原理も説明される(158頁~)。経済学は福祉を高めるための社会経済システムの立案が目的(170頁)。極めてシンプルにして中高生にもわかってもらえる内容。手加減しない内容で、基本的な概念の簡明な説明があり、大人も満足だ。2013/05/28
kanaoka 58
8
人間中心の見方に立って資源の最適配分(効率と衡平)のあり方を考える。そのためには、各個人の労働と消費の実現に焦点を絞り、幸福の基準となる機能の達成水準を評価する。根源には、公平性の理念があり、社会的に合意形成できる基準値(規範目標)の設定により、より幸福な社会の実現を論理的に図る。数値は冷たいが、測れるものは改善される。理念を叫ぶだけの単なる熱さは人を惑わせる。格差問題の解消とトリクルダウンのいずれを優先すべきか?人間が持つ、集団のヒエラルキー志向と公平性志向、いずれが強いか?ということかもしれない。2017/04/11
脳疣沼
3
ジュニア新書にしてはハイレベルなものになっている。私がジュニアだったときは読めなかったと思う。普通の新書にしても良いくらい。社会福祉の話になると、どうしても道徳的な精神論が全面に押し出されてしまい、それが逆に反発される要因でもあるが、理論的に説明されると、なかなか説得力がある。2016/05/21
kusano
3
厚生経済学的な話をかじっとこうと思って読んだ.選択論アプローチに対するセンの批判をもとに,福祉評価がどのようになされるべきかについて解説されている.無羨望配分についてはいくつかの本で見たことはあったが平等等価なる概念は初めて見て,なるほどなーという感じ.2013/02/24
りやうくわん
3
新書にも関わらず厚生経済学の先端研究までカバーしている良書。「経済システムは人々の福祉を高めるためにある」という基本原理に従い、「効率」と「衡平」というキーワードを軸に福祉とその改善について経済学的な考え方が説明される。扱われるトピックを挙げれば、センの功利主義批判、機能と潜在能力、パレート効率性、衡平性基準、無羨望配分、平等等価、ロールズ『正義論』、アローの不可能性定理などなど。これらの概念が「効率」と「衡平」の議論と結ばれ、経済学的な思考に親しみがあれば、その展開は一貫していて読みやすい。2011/06/25