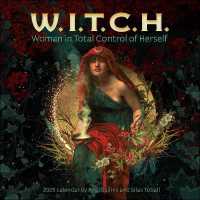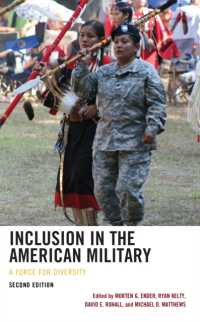内容説明
強制収容所を生き延びた詩人・石原吉郎は、戦争を生み出す人間の内なる暴力性と権力性を死の間際まで問い続けた。彼はシベリアでいったい何を見たのか?石原を軸に抑留者たちの戦後を丹念に追った著者が、シベリア抑留の実態と体験が彼らに与えたものを描き出す。人間の本性、生きる意味について考えさせられる一冊。
目次
プロローグ
第1章 封印された過去
第2章 ラーゲリの記憶
第3章 戦後社会との断層
第4章 詩人へと連なる水脈
エピローグ
付録 三編の詩・石原吉郎
著者等紹介
畑谷史代[ハタヤフミヨ]
1968年、長野市生まれ。早稲田大学文学部卒業、同大学院文学研究科中退。信濃毎日新聞社入社。報道部、文化部を経て現在、論説委員。著書に『差別とハンセン病―「柊の垣根」は今も』(平凡社新書)、共著に新聞協会賞(1999年度)を受賞した『介護のあした』(紀伊國屋書店)などがある(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ステビア
16
石原吉郎の手堅い伝記。2020/08/31
おおかみ
9
戦後の重要な詩人・石原吉郎をテキストに、シベリア抑留が体験者にもたらしたものを読み解く。死の世界を生き延びた石原たち抑留者だが、帰国してもなお救いはなかった。その絶望は石原を屈折させ、唯一無二の詩を編ませた。そんな理解もおそらくは断片的でしかなく、石原が人間なる存在への思索を深め、人生の中に抑留体験をどのように位置付けたのか、戦後80年が過ぎた今、その思考をたどることは容易ではない。何度も読み返す必要があると感じた。作品の数々は忘却の瀬戸際にあるが、それでも確かに影響を残し続けている。2025/10/29
モリータ
9
◆2007-08年の信濃毎日新聞の連載「石原吉郎 沈黙の言葉―シベリア抑留者たちの戦後」をまとめ09年刊。著者は1968年生、同新聞論説委員。詩人・石原吉郎(1915-77)の抑留体験と復員後の詩作・エッセーを軸に、シベリア抑留問題を考える。◆石原吉郎のことを知るにはよいが、ジュニア新書のテーマとしては狭いので、刊行タイトルには難がある気も。◆香月泰男の「シベリア・シリーズ」が挿絵になっている。◆自由を抑圧された人間が、他者を抑圧・侵犯しつつ共生し、生き延びたという、人間性の根源に関する責任、苦悩の昇華。2022/04/01
nbhd
8
石原吉郎その1。とても良いものを読んだ。記者ならではの聞き取りで、沈黙の詩人の肖像が浮かび上がってくる。シベリアで、また日本で、〈人間〉を否定され、みずから否定した果て、言葉を断念したあとに出てくる言葉の数々。はじめての石原吉郎に最適の一冊。ほんとうに良いものを読んだ。2013/02/18
とりもり
7
詩人・石原吉郎に興味を持ち、入門書的に読んでみたのだが、シベリア抑留について何も知らなかった自分に愕然とするほど、その現実は厳しかった。そして何より、その苛烈な日々を過ごしながら待ちわびた祖国に帰った後、その祖国からも受け入れを拒絶されたことが如何に辛かったかは想像に難くない。何よりも、生き延びること=他人を蹴落とすことという、人間の原罪を嫌というほど体験したからこそ、あの言葉を叩きつけるような詩が生み出されたのかと…。生きた証としての「名前」の重さについても深く考えさせられた。オススメ。★★★★★2020/12/27