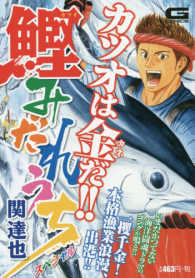内容説明
サッカーのオフサイドやフィギュア・スケートの採点基準など、スポーツにつきもののルールは競技をおもしろくするためにあるのだ、といったらあなたは驚くかもしれない。ルールを通してスポーツが求めるものを探り、さらに私たちの生き方と法の関係を考えていく。著者の説明にスポーツマンの息子が鋭くつっこむ親子対話形式。
目次
第1部 スポーツと法の関係を見てみよう(スポーツから法へ;スポーツにかかわる法;スポーツを支える法)
第2部 ルールはどんな性質をもっているのだろう?(ルールはどこにあるのか;ルールは何を決めているのか;ルールは何のためにあるのか;ルールはどこまでおよぶのか)
第3部 スポーツは何を求めているのだろう?(競争を考えてみよう;公平を考えてみよう;評価の基準とは;国際化すると)
第4部 スポーツと法から社会を見てみよう(観衆とアマチュアがはたす役割;クラブは民主主義の学校;スポーツから裁判を見ると;新しい社会を考える)
著者等紹介
大村敦志[オオムラアツシ]
1958年、千葉県生まれ。1982年、東京大学法学部卒業。現在、東京大学法学部教授、法教育推進協議会委員(座長)。専攻は民法(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ブックウォーカーの提供する「読書メーター」によるものです。
白義
13
スポーツのルールを通して法とスポーツの性質や存在意義を考える独創的な法入門書であり、またスポーツ入門としても優れている。単純にスポーツといっても、そこには常にルールが介在し、またそのルールは法の原型でもある。その競技を競技たらしめる根本から試合の進行、さらには国際化やスポーツ倫理まで、法教育と無縁な部分はほとんどない。抽象的な範囲を扱っているからか即座に身に付くような分かりやすさには欠けるが、新趣向であり前作と繋げて読むと法の輪郭をだいぶ把握できる。それにしても著者の家族は秀才過ぎ2014/05/26
takizawa
4
「死刑判決を下すというのは、私たちの法が死刑を認めているからだね。裁判官でも法務大臣でもなく、私たちが死刑にイエスと言っている。法の名のもとに刑罰が科されるというのは、私たちがそれでいいと思っているということだよね。そのことを確認するのが裁判員になるということだね。」この件は、国民が制度に対して行うモラル・フリーライドに釘をさしているようだ。本書は、中高生への法教育とは、法律そのものを教えることに限らないことを体現している点に意義がある。それにしても玲音君、頭が良すぎる……。2009/02/17
クラッシックラガー
3
法≒競技規則と考えさせる点は見事、わかり良い。スポーツの本来の目的が明確に著されている。スポーツ関係者には、成り立ちやスポーツマンシップについて興味深い内容だと思う。あえて!句読点に「,.」を使うのやめてぇ~「、。」で良いでしょ(芥川賞のABさんごもこれで途中放棄)。親子対談形式なら息子が親に「キミ」と話しかけるのはなんだか。私のようなオヤジを読者層にしていないのかも知れんけど、内容が興味深く面白いだけに、残念。2014/03/16
志村真幸
2
著者は生活や市民社会における法の実践についての研究者。 本書は、岩波ジュニア新書。しかし、誰が読んでも役に立つだろう。 法学者である父親と、相撲をやっている高校生の息子の対話という形式をとっている。スポーツにおけるルールが、どのような役割を果たしているのかが、具体的かつわかりやすく説明されており、競争や公平といったものが、どのようにしてつくられているか理解できる。 さらには、社会生活のなかで一般市民が法に親しみ、実践していく道のりにまで話が及び、壮大だ。2019/08/23
水曜日
2
生徒側に共感できず、会話形式をとっている意味がない。やりとりが気持ち悪く、スッと頭に入ってこない。テーマは面白そうなだけに残念。2018/07/22