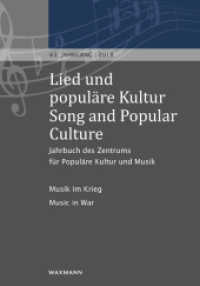内容説明
1個のケーキを二人で分ける方法は?オーダーメイドの手芸店を開くには?ゴミにはどんな値段がつくのか?「こづかいの使い方こそ経済の原点」との立場から、身近なことがらを題材に、子どもたちが参加する経済教室がネット上で開かれた。そこに出てきた情報や意見を紹介しながら、経済とはどんなものかを考え、身につけていける1冊。
目次
帰省ラッシュは解消できるか(希少性と選択)
失敗した買い物は(機会費用)
値段はどうやって決まるんだろう?(市場と価格)
値段のあるもの・ないもの(さまざまな価格)
産地値段は安くない?(裁定取引)
勇者のもちものは?(貨幣)
おこづかいアンケート(所得と財政)
どんな会社をつくるか(企業と起業)
無人島脱出大作戦(比較優位)
ケーキの分け方・つくり方(資源配分・資源分配)
為替市場の風雲児登場(為替レート)
経済が発展する条件は(経済成長)
この格差をどう埋めるか(南北問題と援助)
経済を学ぶと幸せになれるか?
著者等紹介
新井明[アライアキラ]
1949年生まれ。立教大学大学院博士課程前期修了。都立西高等学校教諭
柳川範之[ヤナガワノリユキ]
1963年生まれ。東京大学大学院博士課程修了。東京大学経済学部助教授
新井紀子[アライノリコ]
1962年生まれ。イリノイ大学大学院博士課程修了。国立情報学研究所助教授
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
82
経済の基本的な理論を日常の出来事に結び付けてわかりやすく高校生向けに書かれた新書です。各章の後にはまとめと問題があり、知識をきちんと整理してくれる本です。中学生でも興味のある人にはいいのかもしれません。2015/08/26
kaizen@名古屋de朝活読書会
60
高校の社会と大学の経済学の間には,本書が指摘しているように,差が激しい。 高校で社会が好きだった人も,大学でチンプンカンプンで嫌いになる人もいる。 その間を埋めるのに,本書はとてもよいと思う。 日常生活の中の現象を経済学の理論で考えてみるのに, 個人の行動はミクロ経済学, 社会での集計はマクロ経済学。2011/05/23
スプーン
34
すべてを経済面から考えた本。 半分まで読んだのですが、あまりに自分のポリシーとズレているので、途中棄権。 戦後、すべてを金で考えたから、日本は間違った方向へ向かったのに、 それがいまだにわかってらっしゃらない。 すべてを経済で考える人間(社会)は滅ぶと思ふ。 2020/03/14
肉尊
15
引きこもりの中高生対象と思いきや、同じE教室の他教科の講師が生徒のフリして熱心に受講していたといういわく付きの一冊。機会費用や比較生産費説をはじめビッグマック指数、外国為替相場、所得の再分配など経済の基本をおさえてくれてはいるものの、章ごとの復習問題は、自分で考えてみてね、という解答が多く、具体例を出せないなら出題するなよと思いました。まだ株式会社の最低資本金制度が廃止される前の頃の話。ネットがまだまだ普及する前にやっていた実験的授業の様子が垣間見れます。2021/01/04
鯖
13
第二次大戦について経済学の面から見た本が読みたいなあと思って、何冊かピックアップしたんだけど、そもそも私、経済学さっぱりわかってないやんけ…という訳で付け焼き刃。経済とは「人それぞれ」という観点から、帰省時の高速道路の渋滞、収穫前のキャベツ潰し、勇者のもちもの等、具体的な事例を通して学べて面白かった。経済、まあ教科書なテストは昔も解けてたけど、結局わかったようなわからないような…。2018/11/09
-

- 電子書籍
- 赤い糸に気をつけてください【タテヨミ】…



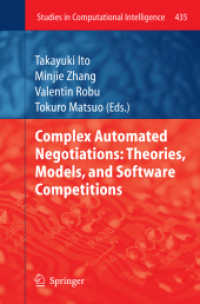
![Parallaxic Praxis : Multimodal Interdisciplinary Pedagogical Research Design [Paperback, Premium Color] (Education)](../images/goods/ar/work/imgdatag/16227/1622737229.JPG)