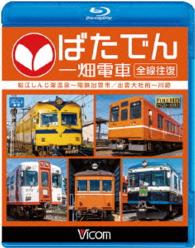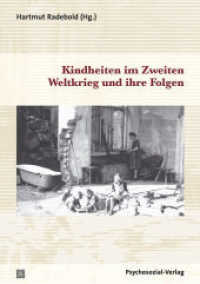出版社内容情報
歴代中国王朝が鋳造した数千億枚に上る銅銭。世界史上極めてユニークなこの小額通貨は、やがて海を越え、日本を含む中世東アジアの政治・経済・社会に大きなインパクトをもたらした。銅銭はなぜ、各国政府の保証なしに商取引の回路を成り立たせてきたのか。貨幣システムの歴史を解明してきた著者が、東アジア貨幣史の謎に迫る。
内容説明
歴代中国王朝が鋳造した数千億枚に上る銅銭。世界史上極めてユニークなこの小額通貨は、やがて海を越え、日本を含む中世東アジアの政治・経済・社会に大きなインパクトをもたらした。銅銭はなぜ、各国政府の保証なしに商取引の回路を成り立たせてきたのか。貨幣システムの歴史を解明してきた著者が東アジア貨幣史の謎に迫る。
目次
第一章 渡来銭以前―一二世紀まで
第二章 素材としての銅銭―一二世紀後半以降
第三章 撰ばれる銅銭―一五世紀以降
第四章 ビタ銭の時代―一五七〇年代以降の日本列島
第五章 古銭の退場―一七世紀以降の東アジア、自国通貨発行権力の始動
第六章 貨幣システムと渡来銭
著者等紹介
黒田明伸[クロダアキノブ]
1958年、北海道生まれ。京都大学文学部卒、京都大学博士(経済学)。京都大学助手、大阪教育大学講師、名古屋大学助教授、東京大学教授を経て、現在―台湾師範大学講座教授、東京大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
パトラッシュ
136
江戸時代までは中国からの渡来銭が使われていたとは日本史の常識だが、元朝が銅貨を廃して紙幣化政策を推進した結果とは知らなかった。しかも渡来銭は貨幣としてだけでなく、銅の素材として輸入されたという。鎌倉の大仏や同時代の寺の梵鐘が、大量の中国銭を原材料に作られたと知れば見る目も変わってくる。また明朝成立後も貨幣不足が深刻化し、広く使用したとされる永楽銭も実は日本で私鋳された贋金が多かった。銭の便利さを知った中世の東アジアで悪銭が必要悪として流通していた実態は、上に政策なければ下が対策をとる逞しさの表れといえる。2025/04/24
skunk_c
82
副題にあるように主な話題は中国の銅銭とアジア諸地域の関わりなのだが、現代の「常識」的感覚とは異なることがたくさん紹介されていてとても興味深い内容だった。特に貨幣数量説では説明できない、最小単位の「原子通貨」(農村や地域市場で流通する通貨)が減少すると、かえって物価が高騰するなど目から鱗。鎌倉の大仏は中国の銅銭が原料だったとか、帆船のバラストに銅銭が利用(陶磁器のことは知っていたが)とか、マリア・テレジア銀貨が20世紀まで中東界隈で流通していたとか。著者の『貨幣システムの世界史』も読んでみたい。2025/12/14
へくとぱすかる
46
銭形平次の投げる一文銭、あれと同類の銅銭こそが、本書のテーマ。平次親分の手元に届くまでに、こんなにも長い歴史があったのかと。金貨なんかより、あれこそが経済の中心なんだと感じた。日本でいえば、江戸の長屋の暮らしにもっとも役に立つのは小判なんかじゃないということだ。それは中国も同じ。中世はいわゆる渡来銭の時代だが、日本で出土する銭の中に唐やベトナムの貨幣と思われるものがあっても、実はそうではない可能性が大きいらしい。そもそもなんで古い唐のお金が? 常識をくつがえすように、そんな疑問を一気に解決してくれた。2025/06/08
よっち
33
歴代中国王朝が鋳造した数千億枚に上る銅銭が、日本を含む中世東アジアの政治・経済・社会に大きなインパクトをもたらした状況を解説する1冊。歴代中国王朝の銅銭はなぜ各国政府の保証なしに商取引の回路を成り立たせてきたのか。12世紀に銅銭が渡来するまでの状況を踏まえながら、素材としての中国銭、元朝の紙幣本位制を機に銅銭が渡来した経緯があって、含有割合で古銭の方がより評価される状況も興味深かったですけど、日本で銅が発見され、倭寇が衰えたことや貫高制から石高制への移行もあって、古銭が退場していく歴史は興味深かったです。2025/04/08
coolflat
20
ⅲ頁。本書が取り上げるのは、およそ12世紀後半から17世紀前半にかけての日本列島を主とする東アジアとその周辺における銅銭の流通についてである。当時の東アジアの人々が取引に使用していたのは中国の銅銭なのであるが、その大多数は北宋の年号を鋳込んだものであった。つまり当時の人々はすでに彼らにとっても「古銭」であったものに頼って売買を行っていたことになる。こと日本においては政府が当該時期に通貨の発行をしていない。それどころか、政府にしてからが、自らの徴税を外国の古銭をもって行っていた。2025/12/20