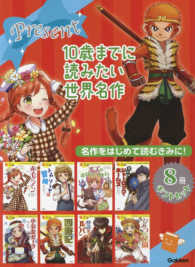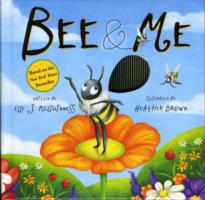出版社内容情報
学校を必要とする社会がつくられ、学校が自明視されることとなった「学校の世紀」を経た今、「教える」ことの意味が鋭く問われている。少子高齢化、多文化化、情報テクノロジーなどによって、教育をめぐる状況が大きく変動したこの一〇年を視野に入れ、新たに描く学校の戦後史。その先に見える、学校の役割とは。
内容説明
学校を必要とする社会がつくられ、学校が自明視されることとなった「学校の世紀」を経た今、「教える」ことの意味が鋭く問われている。少子高齢化、多文化化、情報テクノロジーなどによって、教育をめぐる状況が大きく変動したこの一〇年を視野に入れ、新たに描く学校の戦後史。その先に見える、学校の役割とは。
目次
序章 就学・進学動向からみる戦後―学校の受容と定着
第一章 「日本の学校」の成立―近代学校の導入と展開
第二章 新学制の出発―戦後から高度成長前
第三章 学校化社会の成立と展開―経済成長下の学校
第四章 学校の基盤の動揺―ポスト経済成長の四半世紀
第五章 問われる公教育の役割―この一〇年の動向を軸に
終章 「学校の世紀」を経て
著者等紹介
木村元[キムラハジメ]
1958年石川県に生まれる。1990年東京大学大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。専攻―教育学、教育史。現在―青山学院大学コミュニティ人間科学部特任教授、一橋大学名誉教授(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
源シタゴウ
6
近代以降の学校の歴史を丹念にまとめているが、学校という制度はすでに崩壊しかかっている。 歴史に学ぶことは重要だが、類書は数多くあり、今この時期に読む価値のある本とは思えない。 5章として「問われる公教育の役割」として、2010年以降の山積する問題点に言及している。求められるべきは5章を軸とした対処法であり処方箋であろう。 対処法を考えるべきは現場の教員なのかもしれないが、教育の専門家として、公教育はどのようにあるべきかを示すことも責務だ。2025/05/04
pppともろー
5
近代に生まれた学校。その使命と役割が揺らいでいる現在。平等から選択へ。2025/07/25
田中峰和
5
高度成長期が生んだ豊かさは「戦後循環型教育モデル」と呼ばれ、仕事・家庭・教育という3つの社会領域が複合的な環境要因により、雇用労働の拡大、近代家族化の進行、進学率の上昇を生み出し、それぞれの領域間で循環関係を作り上げた。ところが、90年代の長期不況に入り、正社員の定期採用は抑制され、非正規雇用で代用された。その結果、晩婚化、非婚化、少子化の傾向が強まり、家庭という単位の再生産が滞る。従順な労働力養成のための教育制度も崩壊し、格差が拡がりすぎて、経済成長が鈍化、GDPは4位となった。教育で再生は無理だろう。2025/07/15
U-Tchallenge
3
戦後の学校の歴史について網羅的に書かれた内容であった。学校はそれぞれの時代を経て変わってきているように思う。しかし、それは社会の変化と比べるとかなり緩やかだろう。それは善くも悪くもないように思う。そうは言いつつも負の側面がクローズアップされることが増えてきているように思う。歴史を俯瞰しつつ、少しずつマイナーチェンジを繰り返していかないといけないように思った。最近のことにも触れられているので新版を読むことをおすすめしたい。2025/08/30
Go Extreme
3
歴史総合 近代学校 教えるー学ぶ 国民 臣民 形成 義務教育の成立 新学制の出発 六・三・三制 教育基本法 人格の完成 学校化社会 競争の教育 学習指導要領の法的拘束力 技術・家庭科 学校への反乱 脱学校の社会 学校の動揺 インクルーシブ教育 不登校問題 キャリア教育 総合的な学習の時間 シティズンシップ教育 GIGAスクール構想 学校の公共性 帝国大学 夜間中学 生活綴方運動 集団就職 相対評価と偏差値 大学紛争 高大接続改革 総合的な探究の時間 コミュニティ・スクール 個別最適化された学び2025/04/22