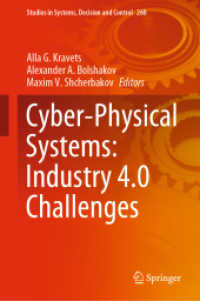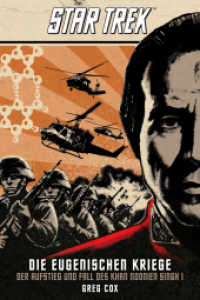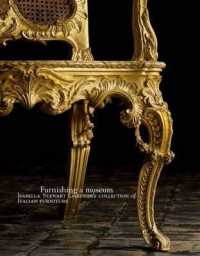出版社内容情報
私たちが日々実践している文字による言語活動は、長い時をへて形づくられてきたものだ。古代における漢字の受容から、往来物による学びの時代へ。近世の文字文化の多様な展開から、近代学校の成立へ。──世界の事例にも目くばりしながら、識字の社会的意味を広くとらえ、今も揺らぎのなかにあるリテラシーの歩みを描く。
内容説明
私たちが日々実践している文字による言語活動は、長い時をへて形づくられてきたものだ。古代における漢字の受容から、往来物による学びの時代へ。近世の文字文化の多様な展開から、近代学校の成立へ。―世界の事例にも目くばりしながら、識字の社会的意味を広くとらえ、今も揺らぎのなかにあるリテラシーの歩みを描く。
目次
第1章 日本における書き言葉の成立(文字以前;文字の借用 ほか)
第2章 読み書きのための学び(習書木簡にみる文字学び;一文不通の貴族たち ほか)
第3章 往来物の隆盛と終焉(近世社会と往来物;庶民用文章型往来物 ほか)
第4章 寺子屋と読み書き能力の広がり(寺子屋というもの;民衆への読み書き能力の普及 ほか)
第5章 近代学校と読み書き(明治期の識字調査;地域内自署率の分布 ほか)
著者等紹介
八鍬友広[ヤクワトモヒロ]
1960年、山形県生まれ。1989年、東北大学大学院教育学研究科単位取得満期退学。博士(教育学)。新潟大学助手などを経て、東北大学大学院教育学研究科教授。専攻、日本教育史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。