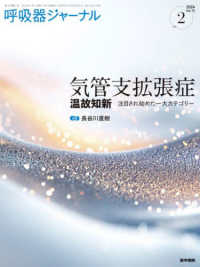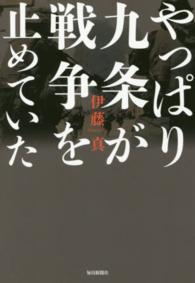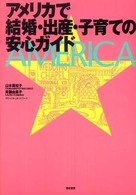出版社内容情報
中西 嘉宏[ナカニシ ヨシヒロ]
著・文・その他
内容説明
ひとつのデモクラシーがはかなくも崩れ去っていった。―二〇二一年におきた軍事クーデター以降、厳しい弾圧が今も続くミャンマー。軍の目的は?アウンサンスーチーはなぜクーデターを防げなかった?国際社会はなぜ事態を収束させられない?暴力と分断が連鎖する現代史の困難が集約されたその歩みを構造的に読み解く。
目次
序章 ミャンマーをどう考えるか
第1章 民主化運動の挑戦(一九八八‐二〇一一)
第2章 軍事政権の強権と停滞(一九八八‐二〇一一)
第3章 独裁の終わり、予期せぬ改革(二〇一一‐一六)
第4章 だましだましの民主主義(二〇一六‐二一)
第5章 クーデターから混迷へ(二〇二一‐)
第6章 ミャンマー危機の国際政治(一九八八‐二〇二一)
終章 忘れられた紛争国になるのか
著者等紹介
中西嘉宏[ナカニシヨシヒロ]
1977年生まれ。東北大学法学部卒業。京都大学アジア・アフリカ地域研究研究科にて博士(地域研究)取得。日本貿易振興機構・アジア経済研究所研究員、京都大学東南アジア研究所准教授などを経て、現在、京都大学東南アジア地域研究研究所准教授。専攻、ミャンマー政治、東南アジア地域研究、比較政治学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
66
『ロヒンギャ危機』(中公新書)の著者が政変と混乱の続くミャンマーについて考えるための現代史を出した。3回のクーデタを成功させた軍政と、その後の民政移管、スーチーの位置づけと役割、そして同国の経済状況など、極めて丁寧に分析されている。前著でもそうだったのだが、スーチーの政治家としての意義と同時にその限界をしっかり捉えている。もちろん軍政と暴力を指示しているものではなく、犠牲になる民衆の立場を重視し、これから先の困難が予想される中、日本の立ち振る舞いにまで提言を進めている。現実主義的だが安直ではない。良書だ。2022/10/25
崩紫サロメ
21
2021年のクーデターについて「なぜこんなことになったのか」ということを主に1988年以降の歴史から描く。ミャンマーは、4回のクーデターを軍トップが主導し、成功させてきた。だが、正統性の主張が困難で統治の困難を生み出した。独裁と民主主義の中間形態である競争的権威主義体制から急速な民主化が進み、スーチー政権が発足したが、それは「軍事政権による制度設計のミスと誤算で進んだ民主化」であったとする(p.260)2022/09/24
ふぁきべ
10
新書だからと気軽に手に取ったが、ミャンマー政治の専門家によるミャンマー近代史を詳細に扱った内容的に非常に重厚な一冊。読み進めるのに苦労するタイプの本ではないが、私もほとんど知らなかったミャンマーの近代史について政治的な背景を中心に扱っていて、かなり参考になった。東南アジア一般として、共産化したヴェトナムや悲惨なクメールルージュ時代のカンボジアなどフォーカスされる時代はあっても一国の独立後の歴史を総括的に扱った本は珍しいので、興味のある人はぜひ、というお薦めの一冊2023/10/15
竹の花
8
2021年のクーデターから2年の節目を前に読めてよかった.アウンサンスーチーの名前程度しか知識がなかった1988年から2021年に至る現代史について独特の政治経済構造を含め平易に解説し,日本の対ミャンマー政策再建にも言及している.著者の示すように見通しは決して明るくないが「忘れられた紛争国」にはしたくない.2023/01/27
Yuki2018
7
東南アジア最後のフロンティアとして期待されたミャンマーだが、昨年のクーデターで振り出しに戻ってしまった。他の東南アジア諸国と異なり、自ら停滞の道を歩む傾向がある。民主化→国家の統合が不安定に→軍が統治強化→停滞で不満が溜まり次第に民主化→統合不安定化…という悪循環を繰り返す「罠」に陥っている。割に合わない解決策を抑制できず、次の段階に進めない。この状況下で軍は大理石の巨大仏像建設に力を入れているとのことで、我々には理解困難な何かもあるのだろう。残念ながら再び成長の道を歩み始めるには時間がかかりそうだ。2022/10/30
-
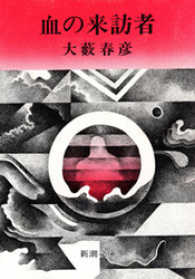
- 電子書籍
- 血の来訪者 新潮文庫