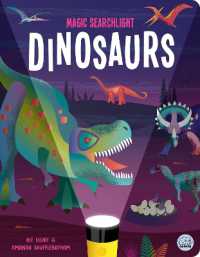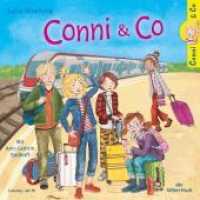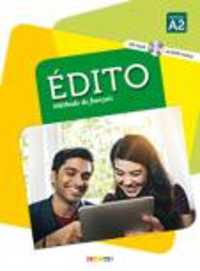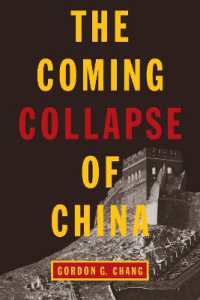出版社内容情報
現代の色彩豊かな視覚環境の下ではほとんど意識されないが、私たちが認識する「自然な(あるべき)」色の多くは、経済・政治・社会の複雑な絡み合いの中で歴史的に構築されたものである。食べ物の色に焦点を当て、資本主義の発展とともに色の持つ意味や価値がどのように変化してきたのかを、感覚史研究の実践によりひもとく。
内容説明
現代の色彩豊かな視覚環境の下ではほとんど意識されないが、私たちが認識する「自然な(あるべき)」色の多くは、経済・政治・社会の複雑な絡み合いの中で歴史的に構築されたものである。食べ物の色に焦点を当て、資本主義の発展とともに色の持つ意味や価値がどのように変化してきたのかを、感覚史研究の実践によりひもとく。
目次
第1部 近代視覚文化の誕生(感覚の帝国;色と科学とモダニティ;産業と政府が作り出す色―食品着色ビジネスの誕生)
第2部 食品の色が作られる「場」(農場の工場化;フェイク・フード;近代消費主義が彩る食卓;視覚装置としてのスーパーマーケット)
第3部 視覚優位の崩壊?(大量消費社会と揺らぐ自然観;ヴァーチャルな視覚)
著者等紹介
久野愛[ヒサノアイ]
東京大学大学院情報学環准教授。東京大学教養学部卒業、デラウエア大学歴史学研究科修了(Ph.D.,歴史学)。ハーバードビジネススクールにてポスドク研究員、京都大学大学院経済学研究科にて講師を務めたのち、2021年4月より現職(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
Porco
10
資本主義社会において、食べ物の色というものがどう変遷してきたのか。食べ物の色がどのように社会的に規定されてきたのか。それを、アメリカをフィールドに記述した本です。こういうものは初めて読みました。2025/06/21
Urmnaf
10
作り手と消費者の距離が近かった時代、作物の色は今ほど重要な情報ではなかっただろうが、遠く離れたところから食べ物が運ばれ、多くの商品から選び、選ばれるようになると、見た目の重要性が増し、着色技術や印刷技術の進歩とも相まって、いわば記号化された「美味しそうな色」が共通の認識としてできてくる。(最近は「映える」色として、そこからの逸脱も起きているが。)何が自然な色か、ということも作られたものだったりする。たいていの農作物は何らか人の手が入ったものだし、何が自然で人工かということがそもそも線引は難しい。2022/01/16
pppともろー
6
とても興味深い考察。食品の色は社会的、文化的、政治的に構築されてきた。視覚の優位性。感覚史。これまで考えたことのない知見にふれられた。2024/05/13
May
4
感覚史の本書では食べ物の色を論ずる。食べ物の自然な(あるべきとされる)色(バナナは黄色等)が生産者や広告代理店によってどのように提示されたのかから始め、これに合わせた農作物、加工食品の生産(バター対マーガリン等)の歴史、小売り段階での色の重要性や見せ方の変化(スーパーマーケット、セルフサービス等)、そして現在の映えまでを扱う。初めに感覚あり、と言うより技術の進歩に合わせて(利用して)来たんだねぇ。”visibleでありながらinvisibleである”色について様々に知ることができ、楽しい読書となった。2024/12/15
おっきぃ
2
食べ物の色がいかに歴史的に社会的に構築されてきたものなのか、自然に見える色が決して文字通りの自然ではないことを論じる。マーガリンの色とか、スーパーの展示が色々な技術に支えれられた上での色の見せ方があるとか、内容としては非常に興味深かった。ただ、本として面白いかというとそうではなくて、あまりにも淡々と事実だけを列挙しているように見えて、読んでいて退屈だったのが残念。2023/01/09