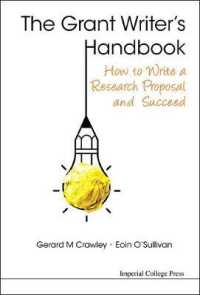内容説明
戦争とファシズムの時代に生きた思想家ヴァルター・ベンヤミン(一八九二~一九四〇)。蹉跌の生涯のなかで彼が繰り広げた批評は、言語、芸術、歴史を根底から捉え直しながら、時代の闇のただなかに、何者にも支配されない生の余地を切り開こうとした。瓦礫を掻き分け、捨て去られたものを拾い続けた彼の思考を今読み解く。
目次
プロローグ―批評とその分身
第1章 青春の形而上学―ベルリンの幼年時代と青年運動期の思想形成
第2章 翻訳としての言語―ベンヤミンの言語哲学
第3章 批評の理論とその展開―ロマン主義論からバロック悲劇論へ
第4章 芸術の転換―ベンヤミンの美学
第5章 歴史の反転―ベンヤミンの歴史哲学
エピローグ―瓦礫を縫う道へ
著者等紹介
柿木伸之[カキギノブユキ]
1970年鹿児島市生まれ。上智大学文学部哲学科卒業。上智大学大学院哲学研究科哲学専攻満期退学。博士(哲学)。上智大学文学部哲学科助手、広島市立大学国際学部准教授などを経て、広島市立大学国際学部教授。専門、ドイツ語圏の近・現代の哲学と美学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
ころこ
59
ベンヤミンの仕事で一番近い形容は、哲学でも思想でもなくて、「批評」でしょうか。彼は「批評する思考が表される媒体としての言語について省察を深め」ます。本書でも、「批評」とそれを表現するための「言葉」が議論になります。けれども、批評を言葉で伝えるのではなくで、「ある言葉が発せられることと、何かが語り出されることが一つになっている。」著者はこれを中動態になぞらえます。ベンヤミンの言葉を使って生じる思考に著者も巻き込まれ気味で、本書の言葉もやや難しいと感じるかも知れません。そのアプローチは、悪くないなと感じます。2019/09/22
ケイトKATE
31
アーレントについて調べていると、ヴァルター・ベンヤミンとの関わりを知り興味を持つようになった。ベンヤミンは批評を小説や詩、哲学といった分野と同等の水準までに高めた人である。ベンヤミンが生きた時代は、二つの世界大戦や世界恐慌、全体主義の台頭など、過酷で破壊の時代であった。ベンヤミンは批評によって鋭い観察と言葉で、闇に葬られていたものに光を当てた。これまで、ベンヤミンの作品を読んだことはなかったが、本書で紹介されているベンヤミンの言葉を読んで作品が読みたくなった。2020/12/06
1.3manen
30
ベンヤミンの批評は、人を死に追いやる神話の呪縛を振りほどく認識として、つねに同時代の状況と向き合っていた。そのうえで「死後の生」を含めた生を、言葉において深く肯定することを彼の思考は目指していた(19頁)。受動と能動の一体性において、ボードレールが語った「万物照応(コレスポンデンス)」の媒体として言語が生じる出来事を、彼は「翻訳」と呼んでいる(80頁)。『ドイツ悲劇の根源』で、批評とは、作品を壊死させることである。2021/05/11
フム
27
ファシズムの時代を生きた思想家。歴史の嵐に揉まれ、ナチスが政権を掌握した1933年以降ドイツから亡命し、ブレヒトやアドルノ、アーレントとの交流があった。副題にもあるが、闇の中を瓦礫を掻き分けるように思考した。その闇に立ち向かう闘いをベンヤミンは批評と名付けた。その批評する媒体としての言語についても、鋭い本質を見抜いている。言語が人々を特定の行為へ動かす「たんなる手段」と化したとき、その空虚な言葉は常套句として増殖し、人々を自動的な反応としての行動に束ねていく、それが総力戦としての戦争の継続を可能にする。2019/12/23
シッダ@涅槃
25
ヴァルターの思想はひとつのこそばゆい思い出と共にあるのだが(西洋現代思想に限定すれば1番読んだ著述家としれない、学生時代)、ひとつの決着を着けようと思って読んだ本。読んでみて「哲学は賭けだ」という思いを抱かざるを得なかった。長大な時間を掛けある哲学者の書を読む。しかし、クロウして読み終えたところで、毒にも薬にもならないからもしれない。あなたの限られた人生を摩耗するだけかもしれない。本書は大変に面白かった。要再読の書。ベンヤミンがフロイト・ユングを批判的にではあれ取り入れていと言うのは知らなかった。2019/12/31
-

- 洋書
- Raphaël
-
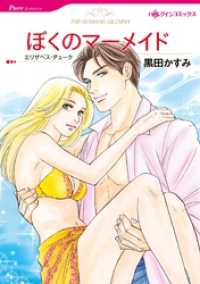
- 電子書籍
- ぼくのマーメイド【分冊】 8巻 ハーレ…