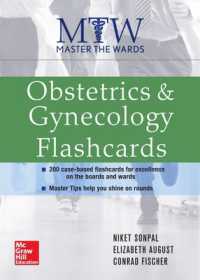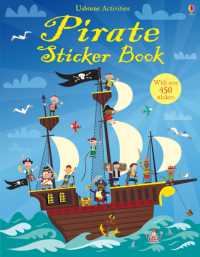出版社内容情報
「戦後労働法制の大変革」とされる働き方改革関連法の内容を盛り込み,定評ある初版を八年ぶりに改訂.
内容説明
「戦後の労働三法制定以来の大改革」とされる働き方改革関連法の施行開始を受け、労働法の基礎知識をわかりやすく提供し、好評を博した初版を八年ぶりに改訂。「働き方改革」の内容はもちろん、初版刊行以後に生じたその他の法改正や判例の展開を盛り込み、大きく発展し続ける労働法の骨格とその背景を描き出す。
目次
第1章 労働法はどのようにして生まれたか―労働法の歴史
第2章 労働法はどのような枠組みからなっているか―労働法の法源
第3章 採用、人事、解雇は会社の自由なのか―雇用関係の展開と法
第4章 労働者の人権はどのようにして守られるのか―労働者の人権と法
第5章 賃金、労働時間、健康はどのようにして守られているのか―労働条件の内容と法
第6章 労働組合はなぜ必要なのか―労使関係をめぐる法
第7章 労働力の取引はなぜ自由に委ねられないのか―労働市場をめぐる法
第8章 「労働者」「使用者」とは誰か―労働関係の多様化・複雑化と法
第9章 労働法はどのようにして守られるのか―労働紛争解決のための法
第10章 労働法はどこへいくのか―労働法の背景にある変化とこれからの改革に向けて
著者等紹介
水町勇一郎[ミズマチユウイチロウ]
1967年佐賀県生まれ。1990年東京大学法学部卒業。現在―東京大学社会科学研究所教授。専攻―労働法学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
佐島楓
おたま
ステビア
大先生
-

- 洋書
- DETROIT ROMA