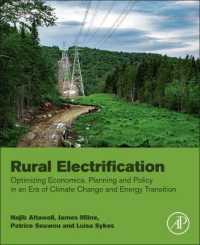出版社内容情報
国を越えた相互交流,漢字文化圏独自の経典,政治・社会・文化との関わりをダイナミックにとらえる通史.
石井 公成[イシイ コウセイ]
著・文・その他
内容説明
紀元前後、シルクロードをへて東アジアに伝えられた仏教は、東から西へ、また西から東へと相互交流・影響を繰り返しながら、各地で花ひらいた。国を越えて活躍する僧侶たちや、訳経のみならず漢字文化圏で独自に創りだされた経典、政治・社会・文化との関わりに着目し、二千年にわたる歩みをダイナミックにとらえる通史。
目次
序章―相互影響の東アジア仏教史
第1章 インド仏教とその伝播
第2章 東アジア仏教の萌芽期
第3章 廃仏と復興
第4章 中国仏教の確立と諸国の受容
第5章 唐代仏教の全盛
第6章 東アジア仏教の定着
第7章 禅宗の主流化と多様化する鎌倉仏教
第8章 近世の東アジア仏教
おわりに―近代仏教への道
著者等紹介
石井公成[イシイコウセイ]
1950年東京都立川市生まれ。1985年早稲田大学大学院文学研究科単位取得退学。現在、駒澤大学仏教学部教授。専攻、仏教と周辺文化(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件