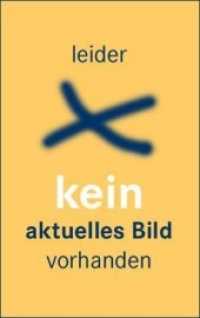出版社内容情報
「公・共・私のベストミックス」の理念のもと、すべての命とくらしを保障する「ベーシック・サービス」を実現せよ 日本の未来を再建すべく、覚悟を持って増税論に踏み込んだ、著者渾身の財政・社会改革の構想の書。
内容説明
なぜ日本では、「連帯のしくみ」であるはずの税がこれほどまでに嫌われるのか。すべての人たちの命とくらしが保障される温もりある社会を取り戻すために、あえて「増税」の必要性に切り込み、財政改革、社会改革の構想を大胆に提言する。自己責任社会から、頼りあえる社会へ―著者渾身の未来構想。
目次
第1章 鳴り響く「一億総勤労社会」の号砲
第2章 中の下の反乱―「置き去りにされた人たち」の怒り
第3章 再分配革命―「頼りあえる社会」へ
第4章 貯蓄ゼロでも不安ゼロの社会
第5章 財政の転換をさまたげるもの
終章 選択不能社会を終わらせる
著者等紹介
井手英策[イデエイサク]
1972年福岡県久留米市生まれ。1995年東京大学経済学部卒業。2000年東京大学大学院経済学研究科博士課程を単位取得退学し、日本銀行金融研究所に勤務。東北学院大学、横浜国立大学などを経て、慶應義塾大学経済学部教授。専攻は財政社会学。著書に『経済の時代の終焉』(岩波書店、2015年、大佛次郎論壇賞受賞)など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
翔亀
46
【人新世11】今、日本で増税を主張するなんて誰が耳を貸すだろう。著者は、そういう租税抵抗が強くなってしまったことこそが日本の不幸だという。減税+歳出削減+規制緩和のセットで何が起こったか。それによって経済成長が達成されたか。歳出削減と民間活力により社会的弱者を切り捨てた(生活保護のカット)。何より大勢の人たちの民意が社会的弱者切り捨てを望んだ。将来の不安ばかりで、他人不信となっているからだ。加えて政治不信があっては増税なんて言えるわけがない、というわけだ。■本書の増税論は、「頼り合える社会」にするための↓2020/12/27
1.3manen
42
はたらいてまずしくなるくらいであれば、どうして生活保護を利用しないのだろう。ここに勤労と倹約の美徳が重くのしかかっている可能性を見だせる(6-7頁)。もし、僕たちが「勤労国家」とはちがう財政モデル、社会モデルを打ちだせる可能性があったとすれば、それは経済が勢いをなくしはじめた1970年代だったのではないだろうか(21頁)と述懐。後悔先に立たず。貯蓄できなければ人間らしく生きていけない勤労国家。それなのに、貯蓄をするだけの収入が得られず、大勢の人びとが将来不安に備える余裕をうしなってしまった社会(27頁)。2019/03/23
みねたか@
30
勤労・倹約を美徳とし、他人の世話になるのは恥とする私たちの文化。生活保護利用者は要件該当者の2割しかいないという。将来不安が高まる中、自己責任概念が他者への攻撃性に高まるギスギスした社会。著者は共存・公正・連帯という大義を掲げ,増税によりベーシックサービスを無償化する再分配革命を説く。2017衆院選民進党の基礎政策を担った著者。結果は小池劇場に翻弄されたが、財政で社会を変えるという気概が清々しい。改革実現には、NPO・市民・地域企業など様々な繋がりの中で、共感と信頼の芽を育てていくことが必要と考えた。2019/08/03
那由田 忠
29
非常に刺激的。左翼的な大企業や金持ちからとればいい論を捨てて、ベーシックインカムでなくベーシック・サービスの導入を説く。日本は、左翼も賛同して「勤労」を国民の義務として掲げ、先進国では日本と韓国くらいの、勤労と自己責任を重んじる「勤労国家」になっている。北欧型福祉国家でなく、全員で痛みを分かちあう消費税を軸とし、富裕層課税を組みあわせると。経済成長が限界となる中で、公共の困難を乗りこえるための国家とその財政を活用し、国・企業・市民が協力し合って命とくらしを保障したいと。財政的数値を出せると説得力があるが。2019/04/23
おせきはん
21
働いても生活保護よりも低い水準の所得しか得られないこともある自助論の限界を踏まえ、ベーシック・サービスの導入を説いています。高齢化の進展に伴い、現在の社会保障の水準を維持するだけでも財政支出が大幅に増えることが見込まれる中で、増税について真剣に検討しなければならないという認識を新たにしました。2019/06/16