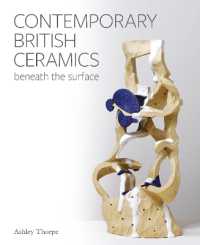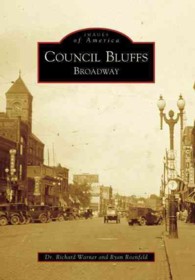出版社内容情報
二五〇〇年前、「目覚めた者」が説いたのは、「自己」と「生」を根本から問い直す思想だった。それは、なぜ古代インドで生まれたのか。現存資料から、口頭伝承された「ブッダの教え」に遡ることは可能か。仏教の原初の世界へ。
内容説明
二五〇〇年前、「目覚めた者」が説いたのは、「自己」と「生」を根本から問い直し、それを通してあるべき社会を構想する教えだった。その思想は、なぜ古代インドに生まれたのか。現存資料を手がかりに、口頭伝承された「ブッダの教え」にまで遡ることは可能か。最新の研究成果によって、“はじまりの仏教”を旅する。
目次
第1章 仏教の誕生
第2章 初期仏典のなりたち
第3章 ブッダの思想をたどる
第4章 贈与と自律
第5章 苦と渇望の知
第6章 再生なき生を生きる
著者等紹介
馬場紀寿[ババノリヒサ]
1973年、青森県生まれ。2006年、東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。現在―東京大学東洋文化研究所准教授。専攻―仏教学(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
HANA
69
原始仏教の解説書。前半は仏陀当時の教えを上座部仏教の経典から文献学的に辿ったもので、楽しめたけど読むのにはある程度の専門知識がいるかも。幸いにもインド哲学について勉強した事があるため、ある程度は読みこなせたけどそれが無ければ手に負えなかったかも。後半はそれによって導き出された仏陀の教えを縁起や四諦八正道、六根十二処十八界をキーワードに解説している。前半に対してこちらは非常にわかりやすくまとめられている。特に仏教が解脱やカースト等、それまでの印度思想を換骨奪胎したという指摘には目から鱗が落ちる思いであった。2019/03/20
へくとぱすかる
57
紀元前の仏教は「宗教」らしいところが、あまりない。全能な神を否定しているし、祈りや祭祀で救われるとも考えない。想像するほど決まりも厳しくない。要は少しも神秘的でない。しかし本書を読めば、初期仏教には、驚くほどよく考えられた教義があり、むしろ哲学を実践する共同体という印象がある。二千数百年の歴史と、伝搬される距離について、深く考えさせられる。2018/08/27
yutaro13
29
初期仏教の思想を歴史的に紐解く試み。仏典の編纂過程はなかなかマニアックだが、スッタニパータやダンマパダといった韻文仏典が、もともと結集仏典に位置付けられていなかった=仏典として権威がなかったとの指摘は興味深い。著者によれば最も古くまで遡れる思想は四聖諦や縁起、五蘊や六処などということになるが、その解説自体は他の本でも読んだことのある内容で目新しさはないような。2019/12/26
サアベドラ
28
ブッダが実際に説いたと考えられる思想を、比較文献学の知見に基づいて仏典から復元し、平易に説明した新書。著者は気鋭の仏教学者(専門は上座部仏教)。2018年刊。前半はブッダが生きた時代背景と周辺思想(バラモン教やジャイナ教など)の解説、および現存する仏典からブッダの時代に近いものを見つけ出す作業に紙幅が当てられ、思想そのものの話は後半になってから。最後の方は結構込み入った内容になっているが、きわめて論理的に書かれているため注意深く読めばついていけるはず。初期仏教のイメージをアップデートすることができる良書。2018/12/27
かふ
24
前半が初期仏教をどのようにして解明していくか?という歴史。いままで口承で伝えられていた初期仏教の最古の経典として、中村元『ブッダのことば(スッタニパーダ)』は最も古いとされてきたが、韻文仏典は必ずしも先行する仏典ではなく外部で成立したものだった。韻文仏典から散文仏典(三蔵)という成立過程は現在では疑問視されている。インド本土で仏教は衰退して部派の資料は大半が失われたが、スリランカや東南アジアに伝わった。バーリ三蔵(律蔵・経蔵・論蔵)の元はスリランカの上座部大寺派が伝えた。2019/11/23
-

- 洋書
- HORS-BORD