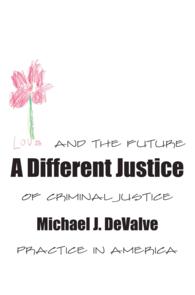出版社内容情報
武士発生の契機、戦場の実際、「武士道」の登場──歴史学の最新の成果をもとに描く「武国・日本」の実像。
内容説明
鎧兜に身を固め、駿馬で戦場を駆けめぐり、刀をふるっては勇猛果敢に斬り結ぶ。つねに「武士道」を旨とし、死をも怖れず主君に忠誠を誓う―そんな武士の姿は、はたしてどこまで「史実」か?日本は本当に「武士の国」なのか?長年武士研究を牽引してきた著者が満を持して書き下ろす、歴史学が見出した最新の武士像。
目次
序 時代劇の主役たち
第1章 武士とはなんだろうか―発生史的に
第2章 中世の武士と近世の武士
第3章 武器と戦闘
第4章 「武士道」をめぐって―武士の精神史
第5章 近代日本に生まれた「武士」―増殖する虚像
終章 日本は「武国」か
著者等紹介
〓橋昌明[タカハシマサアキ]
1945年高知市に生まれる。1969年同志社大学大学院文学研究科修士課程修了。滋賀大学教育学部教授、神戸大学大学院人文学研究科教授を経て、神戸大学名誉教授。博士(文学、大阪大学、2002年)。専攻は日本中世史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 2件/全2件
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
佐島楓
64
常識とされてきた武士像は、かなりの割合で近代以降に作り上げられてきたことがよくわかる。丁寧に歴史を追い、検証しているので、わかりやすい。こういったこれまでの常識を覆す書物がこれからも出てくれることを望む。2018/05/26
ホークス
44
2018年刊。武を能とする者の歴史。濃厚な読み応え。体制史は(私なりの理解では)、①平安中頃まで貴族の中で文・武を分担 ②摂関家や院が地方地盤を持つ京武者を重用 ③平清盛が朝廷の同盟者に ④源頼朝が朝廷の庇護者に ⑤室町期に武士の領主権が確立し、将軍は国の為政者に。朝廷系の侍や平民出の侍も順次組み込まれた。戦闘史は、心理や武器を含め実例を示して論じる。初戦では誰もが意識朦朧である事実など、洞察が興味深い。精神史は、武士道の考察が難しかったが、人の抱える矛盾を直視してキレイ事にしない著者の姿勢には共感した。2024/02/03
エドワード
39
大河ドラマは戦国と幕末しかやらない。来年は昭和だけど。ステレオタイプな信長や秀吉像が出来ていて、そうじゃないと視聴者から抗議が来る。学校の歴史の授業では、わかりやすく説明するため、乱暴な時代区分をする。鎌倉時代から幕末まで、武士政権が続いたように思えるが、朝廷だってずっとあるんだぞ。日本はサムライの国じゃない。武士道は近代生まれの<創られた伝統>。日露戦争後の印象操作が今に至り、日本人は勇敢という偽のイメージが出来る。侍スピリットでガンバレ!という応援は噴飯物という指摘が面白い、いや、とっても大事だ。2018/09/12
さきん
38
平家幕府論で有名な著者。本書ではトーンダウンしている。武士の発生経緯だが、在郷の豊かな農民や領主から始まったわけだはなく、今の自衛隊のように、技能として、専門に訓練した人が、国に雇われて辺境地に赴任したのが始まり。その内に世襲が起こる。皆がイメージする在郷の有力者が武士になるタイプは室町時代の戦乱期に起き、戦国時代に全盛期を迎えた。切腹も北条氏滅亡がきっかけ。死と直面する地位ではあったが、死を好むといった江戸時代の観念とは全く違い、必要とあれば、臆面もなく逃げたし、裏切ったりしていた。2019/01/13
Francis
16
3年間積読。武士に対する世間様の常識ほどあてにならないという事がよく理解できた。以前は東国の農民が自ら武装したことが武士の起源であると言われたものだが、実際には特定の家柄の「武芸」に秀でたものが武士の起源であることや、「二君にまみえず」は江戸時代行政官僚化した武士の職業倫理で鎌倉・室町・戦国時代は主君を変えるのは当たり前であったりとこの本を読めば見方が大きく変わるだろう。2021/07/02