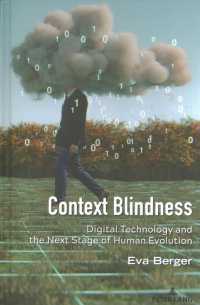出版社内容情報
文字資料だけでなく、聞き取りによる歴史の重要性に光が当てられて久しい。しかし、経験を語り、聞くという営みはどう行われてきたのか。幕末明治から現在まで、語った言葉が歴史として紡がれる現場をたどり、歴史学の可能性を展望する。
内容説明
文字史料だけでなく、聞き取りによる歴史の重要性に光が当てられて久しい。しかし、経験を語り、聞くという営みはどう紡がれてきたのか。幕末明治の回顧、戦前の民俗学、戦争体験、七〇年代の女性たちの声、そして現在…。それぞれの“現場”を訪ね、筆者自身の経験も含め考察、歴史学の可能性を展望する初の試み。
目次
第1章 声の歴史をたどる―幕末維新の回顧録から柳田民俗学まで
第2章 戦後の時代と「聞く歴史」の深化―戦争体験を中心にして
第3章 女性が女性の経験を聞く―森崎和江・山崎朋子・古庄ゆき子の仕事から
第4章 聞き取りという営み―私の農村調査から
第5章 聞き取りを歴史叙述にいかす
第6章 歴史のひろがり/歴史学の可能性
著者等紹介
大門正克[オオカドマサカツ]
1953年千葉県生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士課程単位取得。博士(経済学)。横浜国立大学大学院国際社会科学研究院教授。専攻は日本近現代史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件