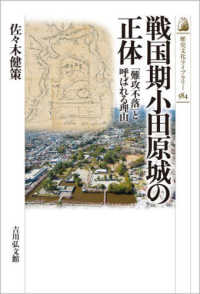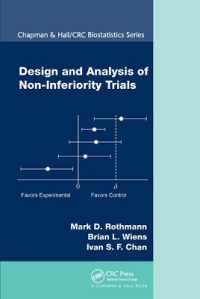出版社内容情報
中世イタリアの商人たちの帳簿、近世オランダや近代イギリスの簿記書から見えてくる、会計の必要と魅力。複式簿記から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書まで、八〇〇年にわたる会計の世界へようこそ。
内容説明
会計―現代の必須スキルの一つと言われながらもついつい敬遠してしまう。本書は中世イタリアの商人たちの帳簿、近世オランダや近代イギリスの簿記書を紹介しながら、財務諸表の誕生とその本質を探る。複式簿記から、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書に至るまで、八〇〇年にわたる会計の世界。
目次
序章 複式簿記のルーツを探る―ルネサンス前夜
第1章 複式簿記の誕生―債権債務の備忘録
第2章 複式簿記の完成―有高計算を帳簿記録で検証
第3章 世界最初の簿記書とその後の進化―年次決算の確立に向けて
第4章 会計学の誕生―決算書類の登場と会計士
第5章 キャッシュ・フロー計算書―利益はどこに消えたのか
終章 会計の本来の役割―会計学と経済学の違い
著者等紹介
渡邉泉[ワタナベイズミ]
1943年神戸市に生まれる。関西学院大学商学研究科博士課程満期退学後、大阪経済大学専任講師、助教授、教授をへて、日本会計史学会会長、大阪経済大学学長を歴任。現在、大阪経済大学名誉教授、商学博士。専攻は会計史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
大きな森の小さな本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
KAZOO
82
どちらかというとこの新書の性格からすると、会計学のノウハウというよりも当然のことながら会計に焦点を当てた経済史のような本だと思いました。私も学生時代は会計学というと無味乾燥な感じがして苦手な科目であったことを思い出しました。ただこの本はそのような歴史を13世紀から説き起こして、最近のリーマンショックやFASBなどについても触れられているのでエッセンスは最低限あるものと思われ入門書としていいという気はしました。2017/12/01
k5
46
名著。複式簿記が誕生した14世紀のイタリアから、近世のオランダ、イギリスを経て、現在のアメリカへ。やはり経済史はロマンがあって好きです。読みながら、「会計は意志です!」という、新人のころに聞いた会社のセンパイの言葉が頭を巡っていました。思えばけっこうアンビバレンツで、哲学のない会計が骨抜きである一方、想いを込めすぎても粉飾に繋がるので注意が必要です。終章における、金融視点が入りすぎた未来会計(discounted CFとか)を批判する部分は読みでがあります。2020/05/27
Francis
19
「帳簿の世界史」に続いて読んだ複式簿記・会計学の歴史。内容は似ているところが多いのだが、こちらではエンロン事件やリーマン・ショックを生んだ会計の機能不全に陥った原因を企業経営者が株主に説明するために損益計算に未来予測を組み込んだ点に求めているのが特徴。「帳簿の世界史」とともに複式簿記の意義がよく理解できた。ますます複式簿記や会計学を学びたくなった。2018/02/18
C-biscuit
18
図書館で借りる。この本は一風変わった本で、会計についての歴史が書かれている。複式簿記が話の中心であるが、昔の文献などからその解説している内容である。理系の人間はなかなかよくわからない世界ではあるが、技術史など同じような雰囲気の本なのかも知れないと感じた。産業革命や大航海時代などの投資など複雑な金のやりとりが発生し、帳簿と実際が合わなくなるなどが、発生した様子が説明されており、いわゆる黒字倒産などについても良くわかる内容であり、それに対応したキャッシュフロー計算書など新たなものが出てきた経緯も良くわかる。2018/03/02
kawa
18
イタリア、オランダ、イギリス、アメリカ、800年に渡る簿記・会計史。ある程度の基礎知識が無いと理解は難しいが、昨今の会計に対する様々なニーズや不祥事に対して「歴史が教えてくれる会計の根源的な役割でありかつ生成の原点である信頼性の立ち返ることが何よりも望まれます。」という著者の締めの論に賛意。会計が様々なニーズに応えるうちに、どのようにも数字を操作できるという誤解が経営者に生じたとするならば由々しき問題だ。2018/01/20