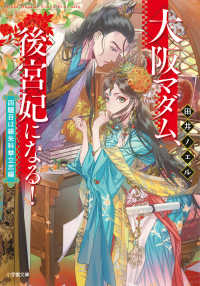出版社内容情報
日米安保体制の歴史と現状を踏まえ、現在の在日米軍の姿を描く。初版刊行から15年。軍事力によらない安全保障は可能か。
内容説明
「専守防衛」を謳いながら今やグローバルに展開する在日米軍の攻撃力に依存し、「唯一の被爆国」は米国の核兵器で守られる―「戦後の平和主義」の現実だ。「緊密で良好な日米関係」を目指すと言う日米同盟の内実は?自衛隊との協力の拡大により変貌する日米安保体制下の在日米軍を直視し、平和構築の道を探る。
目次
序章 在日米軍と日米軍事協力の新段階
第1章 日米安保下の在日米軍
第2章 在日米軍の全体像
第3章 在日米軍の活動を見る
第4章 脅かされる市民生活―基地がもたらす被害
第5章 在日米軍の将来を考える―非軍事の選択にむけて
著者等紹介
梅林宏道[ウメバヤシヒロミチ]
1937年兵庫県生まれ。1965年東京大学大学院数物系研究科博士課程修了、工学博士。1980年大学教員を辞してフリーに。2012年長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)センター長(~2015年)。現在、長崎大学客員教授。NPO法人ピースデポ特別顧問。核軍縮・不拡散議員連盟東アジア・コーディネーター。情報誌『核兵器・核実験モニター』(月2回発行)の主筆(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
稲岡慶郎の本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
skunk_c
20
80才になる著者だが老いを感じさせない健筆ぶりだ。いわゆる9条擁護の論客には軍事的な面の弱い人も散見されるがこの方は例外。本書でも戦略・戦術両面からアメリカ軍を分析している。それに日米の外交・軍事政策を踏まえた視点は確かで、在日米軍を知る基本図書。アメリカ軍の駐留が日本の防衛を目的にしていないことを様々な証拠から明らかにしている。思いやり予算のために、世界の中で本国よりも安上がりに基地が維持できるとのこと。ただ、東アジアの平和構想はやや楽観的すぎないか。側近を次々と粛清する指導者が信用できるとは思えない。2017/07/08
coolflat
12
日米安保体制の歴史と現状、日本の防衛政策の歴史、在日米軍の組織系統や装備等の全体図、在日米軍の活動実態、米兵の犯罪、米軍基地の環境汚染問題や騒音など、網羅的に「在日米軍とは何たるか」を書き記している。30頁。地位協定は、米軍基地の返還義務について「この協定の目的のため必要でなくなった時は、いつでも、日本国に返還しなければならない」と書いている。従って、冷戦終結のような大きな緊張緩和の情勢を受けて、日本政府にその意思があれば、日米合同委員会において基地削減を求める理由は十分に存在し、強力な交渉が可能であった2018/02/03
イボンヌ
8
執筆された2017年時点の最新の在日米軍の配備がわかります。 沖縄県に米軍基地が集中している理由にも言及されています。 ニホンを守るためじゃないのねぇ。2018/08/25
K
3
初版が出版されて15年後の2017年5月、ちょうど北朝鮮のミサイル実験が騒がれていた時期に出版されている。当時読めば良かった…。在日米軍のできた背景、種類、解釈の歴史、問題点など、多岐に渡って詳細に書いてある。比較的最近の話題もあり。記述の仕方も小見出し→トピックセンテンス→説明、と非常に親切で必要な部分だけ拾って読むことも可能。世界的な位置付け、という見方自体、マスメディアからはなかなか得られないものだなと感じた。横須賀の重要性を今まで全然分かっていなかったと反省。苦手分野なので他の著者の本も読みたい。2018/06/20
O. M.
1
在日米軍に関するデータ(基地所在、兵員規模等)、日米安保の歴史、在日米軍の活動、課題などを解説。こういったファクトを新聞、テレビは時々報じてほしい。いや、単に私のアンテナが低いだけならすみませんが。本書によると、在日米軍の目的、機能は、単に日本近辺の防衛から、米軍と共同しての世界の安定へと変化してきているとのこと。政府は諸々の安保関連法制改正の際は、もう少し丁寧な説明と、世論への合意形成が必要ではないかな?2019/01/01
-

- 和書
- 建築/かたちことば