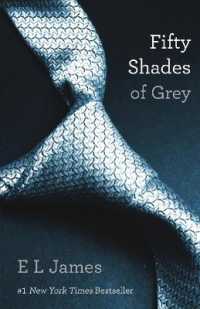出版社内容情報
政党政治を生み出し、資本主義を構築し、植民地帝国を出現させ、天皇制を精神的枠組みとした日本の近代。バジョットが提示したヨーロッパの「近代」概念に照らしながら、これら四つの成り立ちについて論理的に解き明かしていく。学界をリードしてきた政治史家が、日本近代とはいかなる経験であったのかを総括する堂々たる一冊。
内容説明
政党政治を生み出し、資本主義を構築し、植民地帝国を出現させ、天皇制を精神的枠組みとした日本の近代。バジョットが提示したヨーロッパの「近代」概念に照らしながら、これら四つの成り立ちについて解き明かしていく。学界を主導してきた政治史家が、日本近代のありようについて問題史的に考察する重厚な一冊。
目次
序章 日本がモデルとしたヨーロッパ近代とは何であったか
第1章 なぜ日本に政党政治が成立したのか(政党政治成立をめぐる問い;幕藩体制の権力抑制均衡メカニズム ほか)
第2章 なぜ日本に資本主義が形成されたのか(自立的資本主義化への道;自立的資本主義の四つの条件 ほか)
第3章 日本はなぜ、いかにして植民地帝国となったのか(植民地帝国へ踏み出す日本;日本はなぜ植民地帝国となったか ほか)
第4章 日本の近代にとって天皇制とは何であったか(日本の近代を貫く機能主義的思考様式;キリスト教の機能的等価物としての天皇制 ほか)
終章 近代の歩みから考える日本の将来(日本の近代の何を問題としたのか;日本の近代はどこに至ったのか ほか)
著者等紹介
三谷太一郎[ミタニタイチロウ]
1936年岡山市生まれ。1960年東京大学法学部卒業。現在、日本学士院会員、東京大学名誉教授。専攻は日本政治外交史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
遥かなる想い
樋口佳之
Shoji
1.3manen
skunk_c