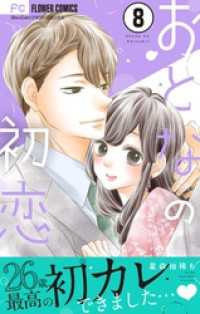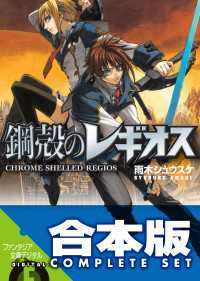出版社内容情報
パウロなくして今日のキリスト教はない。その波乱の生涯をたどり、「最初の神学者」の思想の核心をさぐる。
内容説明
キリスト教の礎を築き、世界宗教への端緒をひらいたパウロ(紀元前後‐六〇年頃)。この人物なくして、今日のキリスト教はないと言っても過言ではない。アウグスティヌス、ルターに多大な影響を与えたといわれる、パウロの「十字架の逆説」とは何か。波乱と苦難の生涯をたどり、「最初の神学者」の思想の核心をさぐる。
目次
第1章 パウロの生涯(生い立ち;謎の青年時代 ほか)
第2章 パウロの手紙(正典としてのパウロの手紙;パウロの手紙はどう読まれたか ほか)
第3章 十字架の神学(イエスの最期;十字架につけられたままのキリスト ほか)
第4章 パウロの思想と現代(パウロの思想の影響;神の啓示をめぐって ほか)
著者等紹介
青野太潮[アオノタシオ]
1942年静岡県生まれ。国際基督教大学、東京大学大学院を経て、スイス・チューリッヒ大学神学部博士課程修了、神学博士号(Dr.theol.)取得。現在―西南学院大学名誉教授、平尾バプテスト教会協力牧師、日本新約学会会長(2009年‐)。専攻―新約聖書学、最初期キリスト教史(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
1 ~ 1件/全1件
- 評価
本屋のカガヤの本棚
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
優希
82
十二使徒ではないパウロ。しかしながら偉大なる伝道者としてその活動は語り継がれています。実際新約聖書の大半はパウロの手紙であると言っても過言ではありません。そんなパウロの十字架の神学は最初の神学だと言えることを教えられた気がします。十字架の使徒として生きたパウロのあり方を知ることで、キリスト教神学の新たな視点を見たような気がしました。2017/07/11
fishdeleuze
35
イエス=キリストはその死をもってわたしたちの罪を贖ったという贖罪論において、つまるところイエスは供犠である。これはユダヤ教的思考であり、復活のキリスト、十字架につけられたままのキリスト、超越者を内在として回心したパウロ(P.108およびガラテヤ書1:15‐17)にしてみれば、神のゆるしや救いを表しきれなかったのだろう。 十字架での磔刑は、弱さや愚かさ、躓き、呪いといった否定的なものの象徴であるが、→2018/01/30
スター
33
元々はキリスト教を迫害する側にいながら、後にキリスト教に転向したパウロにスポットを当てた本。2024/07/02
しんすけ
20
紀元1世紀にパウロという人物が存在しなければ、後にプロテスタントの宗教改革もなかったのでないかと言われる。 だがキリスト教者になるまでのパウロは、敬虔なユダヤ教者だった。そしてローマ市民権も持っていた。 そのパウロが、ローマによって殺されたイエスを発生とするキリスト教に、なぜ改宗したのだろうか。 パウロの中になにか苦悶するものがあったのではないか。 それを期待して読み始めたのだが、そんなパウロを本書のどこにも見出すことはできなかった。2022/11/20
浅香山三郎
18
本書も(以前から積ん読ではあつたが、)『異端の時代』からの流れで読む。生前のイエスには会つてゐないパウロが、キリスト教の布教の中で何を説き、「十字架の神学」をどのように理解したのかを考察する。『異端の時代』でいふ、正典・正統・教義と異端の関係ではないが、パウロの同時代にも様々な教義についての理解があり、いままた、本書のやうにパウロが説いたことについての再検討(贖罪論やイエスの死の理解についての通説への疑問)がある。難解ではあつたが、キリスト教神学がいまも、生きた存在であることを実感させられた。2020/05/16